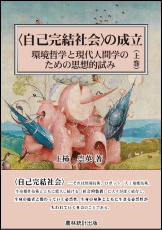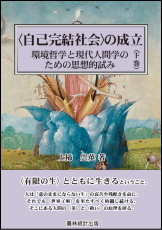『〈自己完結社会〉の成立』(上巻)
【第八章】〈共同〉の条件とその人間学的基盤
(1)人間存在における〈共同〉の概念
さて、われわれはこれまで〈自己存在〉と〈他者存在〉をめぐる「〈関係性〉の分析」という方法論に基づいて、人間存在の本質とは何か、また〈社会的装置〉の〈ユーザー〉となったわれわれの社会的現実がいかなるものになっているのかについて見てきた。
ここからは、こうした〈関係性〉によって成立する人間存在が、現実的な〈生〉の文脈において、いかにして〈他者存在〉との間に協力関係を築くことができるのかという問題、すなわち“〈共同〉の条件”をめぐる問題について議論を進めていきたい。
【第七章】で見てきたように、「〈我‐汝〉の構造」や「〈関係性〉の場」を背負う人間は、「中核的他者」との〈関係性〉において、「相手」が「意のままにならない他者」であるがゆえに、たとえいかなる場合においても、その「内的緊張」に由来する“負担”からは逃れることができない。
〈間柄〉や〈距離〉の仕組みは、負担を軽減させることはできるが、負担そのものを消すことはできないからである。しかし【第五章】において見てきたように、人間が「生きる」ということ、すなわち〈生存〉、〈現実存在〉、〈継承〉を含んだ「人間的〈生〉」を実現していくためには、人間は「ヒト」の誕生以来、常に集団として〈生〉を実現しなければならなかった。
このことを〈関係性〉の次元から捉えるならば、そこで人間は互いに協力関係を結ぶために、〈関係性〉の負担を乗り越える契機がなければならなかったと言うことができる。そしてそれはいかにして可能となるのか、また実際いかにして可能だったのか。本書が〈共同〉という概念を通じて読み解きたいのは、こうした問題についてである。
とはいえわれわれは、最初に、この〈共同〉という概念を整理するところから始めなければならない。というのも、われわれが用いる共同概念は、過去のイデオロギー的な手垢にまみれ、すでに多くの歪みと混乱とを内包したものになっているからである。
まず代表的な辞書によれば、“共同”とは、「二人以上の者がいっしょに事を行うこと」、ないしは「二人以上の者が、ひとつの事物について同等の資格で所有したり、利⽤したり、⼀緒に活動したりすること」を指し、加えて「協同」と同義であるとされている(1)。
“共同”の語源が「共(ともにする)+同(一緒にする)」に由来するのに対して、“協同”が「協(力をあわせる)+同(一緒にする)」に由来することから、“共同”のもともとの意味は「複数の人間が何かを一緒に行うこと」であること、そしてそれを実現するためには「力を合わせる」“協同”が必要になることから、両者が結びつくと考えることができる(2)。
注目したいのは、“共同”概念には前述のように、やや異なる二つの意味合い、すなわち①「何かを一緒に実行する」ための能動的な“行為”に重点を置く意味合いと、②「同等の資格」といったように何かが「共(とも)に同(おな)じ」であること、「同一性」や「同質性」を含む“状態”に重点を置く意味合いが同時に含まれているということである。
語源に即せば、共同の本来の意味は①であることが分かる。本書では、この①の意味での共同を「共同行為」としての〈共同〉という形で改めて定義し、それを人間存在の本質を説明するための基礎概念として整備していくことを試みよう。
最初の問題となるのは、「共(とも)に同(おな)じ」状態を意味する②の含意をどのように理解するのかということである。共同概念は、②の含意があることによって、例えば主人と奴隷の関係のように、その「共同行為」が著しい非対称性によって成立するものではないということを示すことができる。
しかし【第七章】で見てきたように、いかなる人間存在も「差異性」や「異質性」を含む以上、いかなる暴力性も権力性も含まれない〈関係性〉、あるいは原理的な意味において“完全に同質”な〈関係性〉など存在しないのであった。したがって共同概念における「同等の資格」とは、人間的現実を反映するものとしてではなく、あくまで形式的なものとして理解する方が適切だろう(3)。
しかしより大きな問題は、前述したイデオロギーに関わることである。実のところ共同概念は、これまで「史的唯物論」から「アソシエーション論」に至るマルクス主義哲学の系譜を引き継ぐ形で、ひとつの壮大な人間観、歴史観を背負ってきた側面があるからである(4)。
このことを理解するためには、共同概念と、同じように広く用いられてきた“共同性”や“共同体”といった概念との関わりについて考えてみると良い。例えば『哲学中辞典』には「共同性」について次のように書かれている。
- 「社会的存在である人間の相互関係に特徴的なあり方として、多くの社会理論で異なる仕方で説明されるが、しばしば近代の支配的な社会関係と見なされる交換・契約関係と対比的に類型化される。共同の観念は、事実上、社会性一般と等値されるほど広い意味での「人間的つながり」として漠然とイメージされており、その社会関係としての特性に関する理解は論者によって異なる。……共同性が社会成員の相互扶助的で共感的なあり方を指して用いられる場合、共同性観念は理念的に望ましいものと想定され位置づけられている。……この場合、社会がその実現を目指すべき人間的な関係の性格を示すのが共同性というあり方とされる」(5)。
また、『哲学・思想辞典』には、「共同体/共同性」について次のように書かれている。
- 「物質的富や精神的価値を共有すること、あるいはそれらを共有する集団を指す。……近代にこの概念は社会学的なものとなるが、同時に社会概念に対比して歴史化され、共同体/共同性は近代社会の成立によって解体される集団のあり方と規定されるようになる。つまり共同体は、自由な個人の集合体とみなされた近代社会のうちに「失われたもの」として構想される。そのため近代批判の言説はたいていの場合、何らかのかたちで共同体的価値の回復を訴えることになる」(6)。
ここで注目したいのは、多様な解釈が含まれると断りを入れつつも、共同が「事実上、社会性一般と等値されるほど広い意味での「人間的つながり」として漠然とイメージ」されること、また“共同性”が、しばしば「社会成員の相互扶助的で共感的なあり方」を指して用いられると書かれている点である。
共同概念の語源に即せば、“共同性”とは、「共同行為」を行う土壌として人々に共有されている社会的性質とでも呼べそうである。それがここでは、「相互扶助的で共感的なあり方」として理解され、事実上「社会性一般」と同等のものだとも言われている。
ここにあるのは、「共同行為」を相互扶助や共感といった精神に基礎づけたうえで、それが社会的存在としての人間の本性とも言うべき根源的なものであると見なす、いわばひとつの人間観なのである。
次に注目したいのは、そうした共同性が、「近代の支配的な社会関係と見なされる交換・契約関係と対比的に類型化される」こと、また「自由な個人の集合体とみなされた近代社会」の成立によって「失われたもの」として理解されると書かれている点である。
つまり「共同行為」の土壌となる共同性は、ここではまずもって前近代的な社会集団であるところの“共同体”において担保されていたものの、それは近代社会の成立に伴って一度は解体されたと理解される。
そのうえで近代批判の文脈においては、それが「実現を目指すべき人間的な関係」という形、すなわち「回復」すべき価値として位置づけられているのである。ここにあるのは、近代社会を軸に展開される、共同性の喪失と、その再興をめぐるひとつの歴史観であると言えるだろう。
実際われわれは“共同”と聞いて、しばしばかつての農村を想起し、慣習や情緒に包まれた素朴な人々が――あたかも「社会的存在」としての本性が発露するかのように――容易く「共同行為」を実現させていたかのように連想する。そして現代社会の人間のあり方を批判しようとして、しばしばそうした“牧歌主義”とも言える理想郷を想起しながら、「人間的つながり」の回復を訴えてきた側面があるだろう(7)。
しかし重要なことは、そうした反面、“共同体”概念は、しばしば非常にネガティブな概念としても想起されてきたという点である。端的に言えば、共同体は「自由な個性」の埋没したいわゆる「むら社会」を連想させ、その場合は牧歌主義的な理想郷とは正反対に、あくまで変革されるべき前時代的産物として位置づけられているのである。どういうことなのだろうか。
実は、先の歴史観には続きがある (8)。まず、古い共同体には確かに共同性が担保されていたかもしれないが、それがここでは、あくまで「人格的依存関係」、ないしは「同一性」や「同質性」によって成立する共同性であったと理解される。
したがってわれわれの進むべき道は、共同性の「回復」ではあっても、「自由な個性」の埋没した共同体の復興という道ではない。近代社会は、一面においてわれわれに「人格的独立性」を提供したのであって、われわれはそうした「自由な個性」を損なうことなく、共同性をあくまで新しい形で再興しなければならない、という理解である(9)。
つまりここで想定されているのは、単なる牧歌主義には還元されない、共同性と「自由な個性」の止揚――何ものかが何ものかの“否定”として現れ、相互に矛盾するものでありながら、より高い次元においては発展的に統一されること――であって、そうした意味での弁証法的な歴史観なのである(10)。
本書では、この一連のイデオロギーのことを指して「牧歌主義的‐弁証法的共同論」と呼ぶことにしよう。共同概念において、「共(とも)に同(おな)じ」状態を意味する②の含意が根強く存在する背景には、おそらくこうしたイデオロギーの問題も深く関わっているのである。
(2)「牧歌主義的‐弁証法的共同論」批判
前述のように本章の目的は、現実的な〈生〉を実現しなければならない人間が、〈関係性〉の負担を乗り越え、「共同行為」としての〈共同〉を成立させていくことの意味、そしてその条件について明らかにしていくことであった。
われわれは後に、〈共同〉概念を独自の形で再構成していくことになるが、そのためには再度この「牧歌主義的‐弁証法的共同論」と向き合い、批判的な考察を加えておく必要があるだろう。ここではその論点を大きく「自然主義の共同論」、「共同体批判の共同論」、「自由連帯の共同論」という形で析出しながら、順番に述べていくことにしたい。
まず、第一の論点となる「自然主義の共同論」とは、前述のように、「共同行為」を「成員の相互扶助的で共感的なあり方」といった精神(共同性)に基礎づけたうえで、それを「社会性一般」や「人間的つながり」にまで拡張し、社会的存在としての人間の本性とも言うべき根源的なものとして理解する立場のことを指している。
ここで改めて確認しておきたいのは、ここではこうした共同性が、一方では人間の本性として位置づけられながらも、他方では未来に実現されるべき理想としても扱われている点である(11)。そしてその一見矛盾する主張が成立するのは、その背景として、近代社会をめぐる以下のような歴史観があるからであった。
つまり、われわれにとって目の前の社会的現実が、たとえ諸個人のアトム化や孤立化として見えていたとしても、それはあくまで「近代的な交換/契約関係」が支配的になったことによって人間本性が歪められた結果に過ぎないこと――こうした理解はこれまで「疎外論」や「物象化論」と呼ばれてきた(12)――そして人間が根源的に「相互扶助的で共感的なあり方」を志向する存在であるなら、われわれは社会変革を通じてそうした“歪み”を取り除くことによって、人間本来の共同性を取り戻すことができるという理解である。
われわれが【第五章】で見てきたように、人間存在は、確かに生物学的な「ヒト」が成立する以前から「集団的〈生存〉」を行うように進化してきた。また「集団的〈生存〉」を実現するためには、確かに「共同行為」が不可欠であったとも言えるだろう。
そうした意味においては、共同や共同性は、確かに人間の本性であると言えるかもしれない。しかし「自然主義の共同論」の問題点は、人間が生まれながらにして「社会的存在」であることから出発して、その本性を歪める“障害”さえ取り除けば、あたかも人間が“無条件”に共同や共同性を成立させることができるかのように論じてしまうところにある。
われわれはこれまで、〈根源的葛藤〉を克服していくためには、「〈生〉の舞台装置」としての〈社会〉が不可欠であったこと、また「人間的〈関係性〉」を円滑にしていくためには、〈間柄〉や〈距離〉といった仕組みが不可欠になるということについて見てきた。
そのように考えれば、ここでの「社会的存在」への理解や、「相互扶助的で共感的なあり方」という共同性の規定は、「共同行為」の成立過程をあまりに単純化しており、またあまりに予定調和に基づく説明を行っていると言えるのである(13)。
次に第二の論点となる「共同体批判の共同論」とは、一方では前近代的な社会様式としての共同体に理念的な共同性を見いだしながら、他方では「自由な個性」が埋没しているとして、共同体を批判的に捉える立場のことを指している。
実は本書においても、【第四章】において「環境哲学」のアプローチから人類史を俯瞰した際に、「近代的社会様式」が成立する以前の社会様式を指して「都市共同体」や「伝統的共同体」の語を用いてきた。
しかしここでの「共同体」とは、言ってみれば“社会集団”とほぼ同義のものであって、「前時代性」、「人間らしさ」、「同質性」といった一連のイデオロギー的な含意は極力排除しながら論じてきたつもりである。とはいえ共同体という語をめぐるイデオロギー的側面は、実際にはわれわれの想像よりもはるかに強力なものなのである。
まず、前近代的な社会様式を近代社会と対置させ、前者を共同性と結びつけて考える立場そのものについては、K・マルクス(K. Marx)に限らず、19世紀から20世紀にかけての社会思想においては広く共有されたものであった。
例えばE・デュルケム(É . Durkheim)が、前近代社会の特徴を「機械的連帯」(solidarité mécanique)、近代社会の特徴を「有機的連帯」(solidarité organique)と規定したのも、またF・テンニエス(F. Tönnies)が人々を結びつける意志の形式として、前近代社会(=ゲマインシャフト)を「本質意志」(Wesenwille)、近代社会(=ゲゼルシャフト)を「選択意志」(Kürwille)と規定したのも、基本的には同じ対比の枠組みが背後にあると考えて良いだろう(14)。
とはいえ日本語の“共同体”については、やはりマルクスの影響を無視することはできない。
例えば北原淳は、わが国の農村社会学において、大塚久雄の『共同体の基礎理論』(1955)――マルクスが「資本主義的生産に先行する諸形態」として位置づけた諸々の共同体の類型を、一貫した経済理論によって分析した――が与えた影響がいかに大きなものだったのかについて述べている(15)。
つまりわが国においては、大塚を通じて「史的唯物論」に基づく前資本主義的社会類型としての“Gemeinde”が“共同体”として定着し(16)、それがそのまま前近代の象徴としての現実の「むら」に投影されてきた側面がある。そしてそこから「むら」=共同体は、村落社会の実態からは離れ、歴史法則のもとで解体して然るべき前時代的産物として位置づけられていったのである。
ただし共同体に対する批判的な目なざしには、もうひとつ別の文脈が存在していた。それは【第二章】で触れたように、戦後まもなくの日本社会においては、共同体=「むら」が、乗り越えられるべき戦前を象徴するものでもあったということである。
かつて丸山眞男は、戦前日本の基底にあるものを「無責任の体系」と呼んだが(17)、同時代を生きた大塚もまた、あの悲惨な敗戦が、究極的には産業的/技術的な近代化のみに注力し、「近代的人間類型」を支える精神文化の改革を怠ってきた結果であったと考えていた(18)。
つまり共同体=「むら」は、ここでは〈自立した個人〉へと至る、より成熟した精神文化の育成を阻む桎梏、そして一連の悲劇を二度と起こさないためにも打ち破るべきものとして位置づけられていたのである。
したがって、共同体=「むら」を「自由な個性」の埋没と規定し、その共同性を「同一性(同質性)」に見いだす理解は、こうした諸々の思想的背景のもとで形作られてきたと言うことができる(19)。
そして繰り返すように、近代社会を批判するためには、近代社会の“非人間的な側面”を強調する必要があった。そのためこうした文脈においては、共同体は失われた共同性を体現する牧歌主義的理想郷として、今度は逆に過剰に美化され、先の矛盾した二面性を備えるように至ったのである(20)。
さて、この第二の論点の問題点はどこにあるのだろうか。それはまさしく、こうした形で想起されてきた、実態とはかけ離れた共同体の理念の部分である。例えば前述した北原は、次のように述べている。
- 「共同体の代表とされる村落社会には、東西の都市知識人が夢想してきたように、ただ美しい自然と調和的な人間関係だけが残されているのではない。それらは端的にいって大きなコスト、犠牲のもとに成り立ってきた。……このしがらみと無償のコストにささえられて、「むら」の一見すると美しい自然と人間関係は保たれてきた。入会山の美しい自然も、共同労働の無償の人手が加わった結果だった。……ましてや素朴な人間関係の維持については、なおさらである。はた目には美しく映る人間関係の維持は、自然環境の維持以上に、「家」の維持を骨格にした膨大な社会的コストを要し、人の忍従と悲しみの上に成り立ってきた面がある」(21)。
確かに「むら」=共同体は、近代的な産業社会を批判するための対極的な足場として、しばしばあまりに牧歌主意的に捉えられてきた側面がある。そこでは散々“悪”の側に仕立てられてきた「むら」=共同体が、言ってみれば別の何かを“悪”として責め立てるために、今度は無理矢理“善”の側に仕立てられたとも言えるだろう。
したがってわれわれは、そこに付着する「個性の埋没」や、「同一性(同質性)」に基づく共同性というイメージについても、改めて考えてみる必要がある。
例えば前者の場合、そこには確かに、個々人の行動に対して「集団的〈生存〉」を実現させるためのさまざまな制約が存在していたはずである。その意味においては、当時の人々に放縦に振る舞える自由はなかったと言える。しかしそこには固有の利害関心を備え、さまざまな喜楽や悲哀のもとで生きる個体としての人間は存在した (22)。
たとえ外部の人間には「個性の埋没」に見えたとしても、そこには自らの意思を持ち、痛みを感じる人間が確かに存在していたのである。後者についても、はたして何らかの共有された価値や規範さえあれば、集団の「同一性(同質性)」が保証され、あたかも“魔術”にでもかかったかのように、そこでは難なく「共同行為」が成立するなどと本当に言えるのだろうか。
たとえ外部の人間には「同一性(同質性)」に見えるものであっても、それを維持していくことは決して容易ではなかった。北原の言葉を借りれば、そこには「悲しみ」を負った人々による不断の「忍耐」、不断の努力が不可欠だったのである。
そしてここから理解できるのは、「共同行為」のみならず、共同体という社会の枠組みそれ自体もまた、決して“無条件”に成立するわけではないということだろう。
最後に、第三の論点となる「自由連帯の共同論」とは、われわれが目指すべき未来を論じる際、そこでは近代において獲得された「自由な個性」を損なうことなく、共同性を新たな形で再興すること、つまり両者の止揚こそが重要であると考える立場のことを指している。
この論点はある意味では最も重要なものだと言えるかもしれない。なぜならここで用いられる弁証法こそ、共同体概念に付与されてきた先の矛盾を解決するための魔術的なレトリックとなっているからである。
まず、この論点の萌芽が現れるのは、全体主義への警鐘という文脈においてである。そしてその問題意識を象徴するのは、わが国においても広く読まれたE・フロム(E. Fromm)の『自由からの逃走』(Escape from Freedom, 1941)だと言えるだろう。
その内容とは、概ね以下のようなものである。まずフロムによれば、近代社会の成立は、確かに人々に自由をもたらした反面、その代償として、人々から伝統的な社会が与えてくれていた情緒的な人間的結びつきや安心感――それをフロムは「第一次的な絆」(primary bond)と呼ぶ――を剥奪する結果になった。
自ら物事を判断し、決定し、行動していく自由は、単に与えられるままの状態であれば、辛くて重たいものとなる。そこで「第一次的絆」を喪失した人々は、この“自由の重圧”に耐えられず、安心できる“新たな拘束”を求め、やがて外的な権威や権力への依存を自ら選択するようになった。そしてこうした「逃避のメカニズム」(mechanisms
of escape)こそが、20世紀に世界を席巻した全体主義の根底にはあったとしたのである。
ここでフロムは繰り返し警告している。自由は一方で、確かに人々に孤独と不安を課すことになるかもしれない。しかしわれわれはそこで自由から逃避することなく、むしろ強固な意志によってその重圧を引き受け、孤独と恐怖を克服していかねばならない、というようにである(23)。
われわれはこうしたフロム的な人間理解から、共同体=「むら」に対する一連の二面的な理解を乗り越えていく、ひとつの視座を看取することができるだろう。
共同体=「むら」は、確かに人々に安らぎを与えるものだったのかもしれない。しかしわれわれが全体主義の“誘惑”に打ち勝つためには、「自由な個性」を捨てることなく、同時に共同体とは異なる、新たな形の共同性を構築できる道を目指さなければならない。
ここには「自由な個性」と共同性の止揚という論点が、すでに浮上しているのである。
その後、大きな転機がもたらされたのは90年代であった。契機となったのは、この頃情報技術――当時はまだ真新しいものであった――を駆使して組織化を図り、国家行政や市場経済からも独立した形で幅広く活動を展開していくボランティア団体、NGO、NPOといったものが台頭してきたこと、そしてそうした社会組織の存在を新たに意味づける「アソシエーション論」や「公共性(圏)論」が登場したことである(24)。
こうした新しい組織の担い手たちは、共同体=「むら」を支えた土着的で素朴な人々というよりも、都市に住み、知識を蓄え、自らの意志によって連帯していく“市民”であった。端的に言えば、それは当時の人々にとって「自由連帯の共同論」の核心部分、まさしく「自由な個性」と共同性が止揚された姿として映ったのである。
このことを反映するかのように、「アソシエーション論」や「公共性(圏)論」においては、そうした新たな運動や組織が執拗なまでに共同体=「むら」と対比させられていた。
すなわち共同体=「むら」が、「閉鎖性」、「同一性(画一性)」、「強制」、「個人の抑圧(全体主義)」によって基礎づけられるのに対して、「公共性(圏)」の担い手となるアソシエーションこそ、「開放性」、「多様性(複数性)」、「自発性」、「自由な個人による連帯」によって基礎づけられる、といった具合にである(25)。
こうして共同体=「むら」は、一連の二元論のなかに理念的に固定化されていった(26)。そして共同体と近代社会をともに乗り越えていくものとしての、「新しい市民社会」という展望が確立していったのである。
さて、この第三の論点の問題点はどこにあるのだろうか。まず実態としての側面について言えば、2000年代初頭は、確かにこうしたアソシエーションへの期待が高く、いずれはあまねく人々がアソシエーションに参加するようになり、それを通じてあらゆる社会的な問題が解決されていくかのような、ある種の楽観主義さえ見受けられたように思える。
しかしあれから20年あまりが通過して見えてくるのは、こうしたボランティア団体、NGO、NPO等が一定程度社会的に定着する一方で、そうした活動が瞬く間に頭打ちを迎えていく現実であった(27)。しかしより重要なのは、それを安易に「自由な個性」と共同性の止揚として認識してきた、あの弁証法的な人間理解についてだろう。
そのレトリックによれば、一見相互に矛盾して見えるものでも、互いに優れた側面を出し合うことによって相互補完し、より高い次元においては統合されるということになる。
それは確かに、図式としては巧みで美しいものだったのかもしれない。しかしそもそもなぜ、矛盾し合うもの同士が統合可能だと言えるのか。「自由連帯の共同論」はこの点について――後述する「~への自由」や「積極的自由」の概念も含めて――十分な説明を行ってこなかったのである(28)。
実際アソシエーションをめぐる議論においても、散見されるのは予定調和を前提とした賛美ばかりで、いかにしてアソシエーション自体が成立しえるのか、またなぜそこでは〈共同〉が可能となるのかについて、人間的現実を踏まえた説明がほとんどなされてこなかった。具体的に指摘しよう。
例えばそこでは、アソシエーションが“自由”と“自発性”に基づく連帯であると言う。しかしそこで「共同行為」を成立させるにあたって、“抑圧”や“強制”の芽がないなどと本当に言えるのだろうか(29)。またそこでは、地道な啓蒙さえ続けていけば、あるいはより多くの政府の支援や人々の自由時間さえあれば、そうした活動が全面的に展開する「アソシエーション社会」が実現すると謳われてきた。
しかし自由と自発性を強調するのであれば、そもそも関心が合致しない人間による不参加の意思、連帯自体を拒絶するという自由の行使は、いかなる形で理解すれば良いのだろうか。仮にそうした人々の意思を尊重しないと言うのであれば、それは彼らが根絶しようとしてきた抑圧や強制と何が異なるのだろうか。
要するに、われわれの社会的現実においては、「自由な個性」と共同性の止揚という理念的想定も、「アソシエーション社会」という新たな理想郷も、根底においてはすでに破綻してしまっているのである。
(3)〈共同〉概念の再定義
以上を通じてわれわれは、「牧歌主義的‐弁証法的共同論」の内実について詳しく見てきた。
われわれはここで、一連の論点に共通する根源的な問題点があったことに気づかされるだろう。それは共同という行為を実現するために人々が受け入れなければならない負担、それを一連の議論がほとんど顧みてこなかったということである。
われわれが【第七章】において見てきたように、〈他者存在〉とは根源的に「意のままにならない存在」であるために、〈関係性〉には必然的に負担が伴う。しかしそのことは、人間を無条件に「相互扶助的/共感的」と規定する牧歌主義、あるいは弁証法という魔術的なレトリックによって隠蔽され、われわれの共同理解に対して多大な歪みをもたらしてきたと言えるのである。
したがって、負担なき共同とは虚構であるということ、この命題こそがわれわれの人間理解において根底に据えられなければならない。
ここからは、これまで原理的な次元においてしか捉えてこなかった〈関係性〉の負担という問題を、改めて「複数の人間が何かを一緒に行うこと」を意味する「共同行為」としての〈共同〉の文脈において捉え直してみたい。そしていくつかの思考実験を織り交ぜることによって、この命題がなぜ人間の〈共同〉を考えるうえで不可欠なものだと言えるのかについて見ていこう。
さて最初に、あるところに“100人”のみによって構成された「村」があることを想像してみてほしい。そしてそこではすべての「村人」が、一切の抑圧や強制がない状態で、無制限に「自己実現」を目指すことが約束されているとしよう。
つまりここでは無条件に、音楽家になりたい人間は音楽家になり、陶芸家になりたい人間は陶芸家になることができる。「牧歌主義的‐弁証法的共同論」からすれば、これは「理想的な村」となるはずである。
なぜならここでは、人々はかつてのように、生まれや育ち、イエや慣習、身体的差異や経済力といったものに縛られることがなく、あらゆる局面において個人の自発性と自由選択が尊重され、その結果、開放的で多数性に富んだ「村」になることが保障されているからである。
象徴的な言い方をすれば、そこでは人々は「おのれの人生の主人公」となること、「自由な個性の全面的な展開」が約束されているのである(30)。
しかしこうした「100人の村」は、おそらく早晩に破綻するだろう。そしてその理由は、さほど難解なものではない。というのも人間存在には、〈生〉を実現してくために不可欠となる事柄があり、しかもそれは、しばしば「誰もが恩恵を受ける可能性があることだが、誰もが自発的にしたいとは思わないこと」であること、そしてこの「村」では、自らの意思に反して何かを行うことは、直ちに悪しき抑圧や強制として理解されてしまうため、誰一人としてそれを引き受けるものがいなくなるからである。
もちろんこうした危機を察知して、その負担を担おうとする“有志”が現れることは十分に考えられる。しかしそうした有志も、おそらくやがてはいなくなる。なぜならこの「村」においては、有志の取った行動は、理論的にはまさしく自発的な行動として理解されるのであって、そのため敢えてそれに続こうとするものが出てこなくなるからである(31)。
具体的に考えてみよう。例えばここで限界に達した有志が、ついに他の三人の「村人」に向かって次のように言ったとしよう。「私が散々背負った負担をあなた方も背負うべきではないか」。
それに対して三人が、それぞれ次のように返答したらどうだろうか。すなわち「それは私が頼んだのではなく、あなたが自発的に行っていたことであったはずです。それをなぜ私に強制するのですか」、「私には難しいです。なぜならそれを行うことは、私の内面(価値意識)に反するからです」、「お断りします。私自身の考えでは、それは必要であるという結論に達していないからです」といったようにである。
おそらく有志は、ここで反論することができない。なぜなら一切の抑圧や強制があってはならないとする「村」の前提からすれば、三人の言い分はいずれも正当なものだと言えるからである。こうして「村」は崩壊し、そこには誰もいなくなるのである。
この「100人の村の比喩」は何を物語っているのだろうか。それは、すべてが自発性と自由選択にのみ任される世界においては、人々の間で「共同行為」のための負担を引き受ける必然性は成立せず、その集団は持続的にはなりえないということである(32)。
ただし驚くべきことに、唯一それが可能な世界がある。それは何らかの〈社会的装置〉――ここではそれが「奴隷」かもしれないし、「ロボット」かもしれないが――に、その「誰もが恩恵を受ける可能性があることだが、誰もが自発的にしたいとは思わないこと」をすべて肩代わりしてもらえる世界、皮肉にもわれわれが〈自己完結社会〉、あるいは〈生の自己完結化〉や〈生の脱身体化〉と呼んできたものが極限にまで進んだ世界に他ならない。
そこでは誰もが、他者からの嫌な介入を受けることなく、永遠の「自己実現」を続けることができる。当然、50人が音楽家になることも、99人が陶芸家になることも可能だろう――もっとも、そのような世界で人々が音楽家や陶芸家として生きることに“意味”を見いだせるかどうかは定かではないが――。
次に、一連の思考実験に対していくつかの“ひねり”を加えてみることにしよう。まず「村人」は、この「村」を出ていくことができないものと仮定する。次に、「誰もが恩恵を受ける可能性があることだが、誰もが自発的にしたいとは思わないこと」の例として、ここでは「共有地の掃除」というものを導入する(33)。
さらにここでは、「村人」全員が極度な掃除嫌いであること、また「掃除」をしなければ、不衛生から全員が病気になると仮定しよう。そうすると、「村人」が生き残っていくためには、誰かが必ず意に反してまで、「掃除」を引き受けなければならないことになる(34)。「村人」はどうするのだろうか。
この問題を解決するひとつの方法は、「共有地」を均等に分割し、あとは自己責任とすることである。そうすれば「病気になる」という結果を被るのは、「掃除」をしなかったものだけとなるだろう。
ところがここでの「共有地」が、例えば“共用の井戸”のように、分割不能なものであったらどうだろうか。ここから導きだされる結論は、おそらく次のようなものになるはずである。すなわち「掃除」を行う負担を、全員で均等になるよう分配するということである。
ここで新たな条件として、「村人」には“差異”が存在し、身体的に不自由な人間がいると仮定してみよう。その場合、おそらく文字通りの均等な分配は賢明な方法とは言えなくなる。次善の方法として、例えば特定の「村人」には「掃除」を免除する代わりに、別の局面おいては、より多くの負担を引き受けてもらうということになるかもしれない。
だが、いずれにしても、この「村」にはかつての面影はないだろう。なぜなら「村」は、すでに一切の抑圧や強制が存在しない「村」ではなくなっているからである。
例えば「掃除」を蔑ろにする人間がいれば、当然他の「村人」からは嫌われることになり、それを怠ったものがいれば、当然集団的な制裁が課されることが予想される。また負担を分配する際、誰が何をどれだけ負担すべきかということに対して、唯一の正しい“正解”はない。
それゆえ「村人」たちは、辛抱強く互いの立場、利害、感情に対する理解を深め、負担のあり方をめぐって、できうる限り多くの人間が納得できる形を導きだすことが求められる。しかも多くの場合、われわれは限られた時間のなかで何かを決断しなくてはならない。したがってそれが、常に構成員全員の納得――換言すれば“自己決定”――を得られるものとして導けるとは限らないのである。
この「掃除当番の比喩」は、われわれに何を物語っているのだろうか。それは、「共同行為」を成立させるためには、人間は、ときに自らの意思に反して何かをしなければならない場面があるということ、そしてときに納得を欠いた状態であっても、何かに参加しなければならない場面があるということである。
逆に言えば、「牧歌主義的‐弁証法的共同論」では、「自由な個性」と共同性の止揚が予定調和を前提に語られるばかりで、こうした事態が一切想定されてこなかったと言えるのである(35)。
以上の思考実験を踏まえ、ここでは改めて、本書における〈共同〉の概念について整備してみよう。
まず〈共同〉とは、「複数の人間が何かを一緒に行うこと」を指すのであった。もちろんここでの「共同行為」が、同一の場所、同一の時刻に、また同一の内容において行われるとは限らない。「共同行為」は、しばしば相互に分担しあうことを通じて、何かを有機的に実現する場合があるからである。
ただし、この規定だけでは、人間存在の〈共同〉を捉えるにあたって未だ不十分である。なぜなら〈共同〉とは、人間存在が〈他者存在〉とともに何かを協力して実践していく行為であるだけでなく、ここで見てきたように、それに伴って必然的に発生する負担をともに引き受け、そのうえで何かを実現させていく行為だからである。
つまり〈共同〉概念の本質を理解する鍵は、この“負担”というものをわれわれがいかなる形で理解するのかということにあるのである。例えばその負担のなかには、前述の「掃除」のように、行わなければならない具体的な作業や行為の内容が含まれているだろう。そしてそれが負担となるのは、しばしばそれが「意に反して」行われるものとなるからであった。
だが〈共同〉において最も重要となる負担は、むしろ別の所にあるだろう。すなわちそれが、必然的に〈他者存在〉との対峙を要請すること、つまり「意のままにならない他者」と向き合わなければならない負担、さらに言えば、そうした〈他者存在〉と負担を分け合っていく方法を模索していく過程自体がもたらす負担こそ、〈共同〉の負担の核心部分に位置するものだと言えるのである。
(4)〈共同〉が成立するための諸条件
それでは人間存在にとって、〈共同〉が成立するための条件とは、いかなるものになるのだろうか。つまり、人々がそうした〈共同〉の負担に耐え、協力関係を構築することができるのだとすれば、それは何に由来するのか、あるいはその負担を「遠心力」とするならば、それに抗しつつ人々を〈共同〉へと向かわせる、「求心力」となりうるものは何かということである。
結論から先に述べれば、〈共同〉が成立するためには「〈共同〉のための事実の共有」、「〈共同〉のための意味の共有」、そして「〈共同〉のための技能の共有」という三つの条件が満たされなければならない。ここでは、そのことついて見ていくことにしよう。
まず、〈共同〉の第一条件となる「〈共同〉のための事実の共有」であるが、それは構成員の間で、その「共同行為」が互いの〈生〉にとって重要であるという事実認識が共有されているということを指している。
例えば先に「掃除当番の比喩」について見た際、われわれは敢えて、そこで「村人」は「村」を出ていくことができないものとして仮定した。実はこのことが、この第一条件と密接に関わっている。というのもこの前提があることによって、「村人」たちは、その「共同行為」が互いの生にとって不可欠であるという“事実”を等しく共有できるようになるからである。
またこのことは、われわれが【第五章】において「人間的〈生〉」を分析した際、なぜ繰り返し、最も根源的な契機は「〈生存〉の実現」であると強調してきたのかということとも深く関わっている。というのも「人間的〈生〉」においては、原始以来〈共同〉の成否が「〈生存〉の実現」に直結してきたということ、そしてまさにその事実こそが、〈共同〉の負担を打ち消す「求心力」となってきたからである。
とはいえ「求心力」となる事実の内実は、例えば“飢餓の危険性”や“命を脅かす共通の敵の存在”といった極端な事態にのみ限定されるものではない。この条件は、例えば“会合”を開く、どこかに連れ立って“外出する”といった日常的な活動をも含む、あらゆる「共同行為」について一般的に言えることだからである。
重要なことは、あくまで「共同行為」の当事者たちにとって、そこに〈共同〉を行うことで得られる明白な利益の存在が認識として共有されているということなのである。
ただし、このように〈共同〉に「利益」を求めることは、一見われわれにとって“不純”なものとして感じられるかもしれない(36)。とりわけ「牧歌主義的‐弁証法的共同論」のもと「相互扶助的で共感的なあり方」を人間本性と見なす人々からすれば、「利益」を強調することは、われわれが人間に根源的であるはずの“利他性”を否定し、あらゆる人間行為を“利己性”に還元しているようにも映るだろう(37)。
しかし先に見てきたように、無条件に〈共同〉が成立することなどありえない。どれほど崇高な理念によって始動された〈共同〉であっても、それが「利益」を無視したものであるならば、それはときとともに形骸化していき、やがては誰も参加しなくなる。
ここで注意すべきなのは、われわれがしばしば単発的に行使される「利他的行為」と、継続性や持続性が問われる〈共同〉とを混同することがあるということである。
確かに人間は、ときとしてさまざまな文脈のもと、自己への直接的な「利益」を度外視した形での「利他的行為」を行うことがある。しかしそれを継続的、持続的に求めるのであれば、われわれはそれを〈共同〉ではなく、むしろ「博愛主義」と呼ぶべきであろう。
そしてすべての人々にそうした「博愛主義」を要請することは、明らかにわれわれの人間的現実に反している(38)。その意味では、人間の〈共同〉を問題にするうえで、そもそも利己的/利他的という二元的な対抗軸を設定すること自体が間違っているとも言えるのである。
もっとも、前述のフロムであれば次のように言うかもしれない。特定の「共同行為」を人々が「意に反する」と捉えている限り、そこには確かに「利益」が必要である。
しかし人間は自我を成長させることによって、物事の捉え方を変えることができる。つまり真の“個性”、真の“自律”が確立されたあかつきには、皆の利益となる「共同行為」は自らの意思の延長として、まさに“自発的な行為”として昇華されうる、といったようにである(39)。
この着想は、しばしば「積極的自由」(positive liberty)や「~への自由」(liberty to)とも呼ばれ、その背景にはJ・J・ルソー(J. J. Rousseau)からI・カント(I.
Kant)に至る、きわめて長い西洋近代哲学の伝統がある(40)。
それを端的に表現するなら、“真の自由”とは、孤立した自我に従って放縦に振る舞うことでなく、「皆のため」であることが「自身のため」としても感受される境地であり、換言すれば、あたかも他者の喜びが自身の喜びとして、また他者の苦痛が自己の苦痛として感受されるような、まさしく“自己の自由”と“他者の自由”の調和に基づく、より高級な意志を獲得することである、ということになるだろう(41)。
もちろんわれわれは、人間の〈生〉において、ときにこうした「高級な意志」が出現するということを知っている(42) 。しかし人間的現実を冷静に見つめるのであれば、われわれは両者が常に調和していることなどありえないということ、そしてそうした境地を誰もが実践できるわけではないということが分かるだろう。
内に秘めた〈根源的葛藤〉と多様な〈関係性〉の狭間において、意思の「一致」と「不一致」の間を交互に揺れ動きつつ、そのなかで何とか均衡を保ちながら生きていくのが人間だからである。「高級な意志」を全面化しようと思えば、われわれはやはり、すべての人間に「博愛主義」を要請する以外に他はない。
「積極的自由」とは、結局先の弁証法と同じように、抑圧の存在しない世界、あるいは負担なき〈関係性〉や負担なき〈共同〉があたかも可能であるかのように見せかける魔術的なレトリックだと言えるのである。
すでに見たように、〈共同〉において重要なことは、その負担をめぐってすべての参加者の納得が得られるとは限らないなかで、それでも「共同行為」を継続的、持続的に成立させなければならないというところにある。
したがって円滑な〈共同〉の実現においては、参加者の「利益」を問題にすることは、本来恥ずべきことでもなければ、人間存在の利他性を否定するものでもないと言える。むしろ、人の情けや善意というものを活かすためにも、われわれが細心の注意を払うべき事柄だと言えるのである。
だが“事実”の共有だけでは、おそらく〈共同〉は成立しない。そこで次に言及するのが「〈共同〉のための意味の共有」、すなわち構成員の間で、その「共同行為」が互いの〈生〉にとって重要であるということの“意味”が共有されているという第二条件である。
前述の「掃除当番の比喩」で言うならば、「掃除」を行わなければ全員が病気になるという認識こそが、ここでは共有されるべき“意味”となるだろう。もっとも、とりわけ意味の共有が求められるのは、〈共同〉がもたらす「利益」が直接的でなかったり、可視化されていなかったりする場合である。
人間の世界においては、しばしばまったく「利益」になるとは思われない「共同行為」が、巡り巡って最終的には自身や身内の「利益」として還元されたり、集団全体の維持にとって重大な役割を果たしていたりすることがある(43)。こうした場合、その場の瞬間的な「利益」だけを気にかけていては〈共同〉は成り立たない。
持続的な〈共同〉のためには、その〈共同〉がなぜ必要とされるのか、そしてそれがなぜ負担に見合うだけの価値あるものだと言えるのかについて、人々がさまざまな観点から意味を見いだし、その意味を共有していく必要があるのである(44)。
とはいえ、〈共同〉が成立する条件としては、まだ不十分である。そこで最後に言及したいのは、「〈共同〉のための技能の共有」、すなわち構成員の間で、「共同行為」を実現させるためのある種の“技能”が共有されているという、第三条件である。
この「〈共同〉のための技能」を考える場合、最も広い文脈において重要となるのは、負担の分配に関わる諸々の“技能”である。
前述のように、継続的、持続的な〈共同〉を実現するには、参加者は「意のままにならない他者」と向き合い、より多くの人間が納得できる分配の形を導かなければならない。そしてその過程には、多くの作法や知恵を含んだ技能が必要とされる。
例えば人々が互いに意思の疎通を行い、立場や利害、感情への理解を深めるためには、さまざまな“発話の技能”が求められよう(45)。加えて特定の人間に過剰な負担が生じることなく、また特定の人間だけが負担を被らないフリーライダーとなることもなく、なおかつ個別的な事情に配慮した形で分担の構図を描いていくためには、さらに多くの“工夫の技能”が求められるはずである(46)。
そしてそうした技能は、特定の個人に限定されることなく、集団全体として担保されることが理想的であると言えるのである。
【第八章】(5)「〈共同〉のための作法や知恵」としての〈役割〉、〈信頼〉、〈許し〉の原理 へ進む
【上巻】目次 へ戻る
(1)『日本国語大辞典』(2007)項目「共同」を参照。
(2)『日本語源広辞典』(2012)項目「共同」、「協同」を参照。さらに関連する語としては、“協働”=「協(力をあわせて)働(はたらく)」もある。
(3)例えば人間的現実においては、“建前”は「同じ資格」でありながら、実際問題としては対等でないという関係性がいくつもある。しかし「共同行為」において重要なことは、“完全に同質”というものが存在しないからこそ、そうした“建前”が毅然として存在することである。「共(とも)に同(おな)じ」ものとしての共同は、この点からも存在論的な同質性ではなく、あくまで「資格」としての形式的な同一性として理解するのが適切だろう。
(4)わが国のマルクス主義哲学の系譜は、「史的唯物論」から「疎外論」の研究を経由して、「アソシエーション論」へと展開されていったというのが筆者の理解である。まず「史的唯物論」とは、K・マルクス(K. Marx)とF・エンゲルス(F. Engels)が『資本論』(Das Kapital, 1867-1883)などを通じて展開した理論的枠組みのことを指し、そこでは人類の歴史が「生産様式」の発展段階として捉えられたうえで、それぞれの「生産様式」が「階級闘争」を通じて必然的に次の発展段階へと移行すると考えられた。この理論は資本制社会の変革を謳う社会主義思想に絶大な影響を及ぼし、それがV・レーニン(V. Lenin)以降のソ連を中心とした共産主義思想の支柱をなすことになった(そのため「マルクス=レーニン主義」とも呼ばれた)。しかし20世紀後半に入り、ソ連の実態が明らかになってくると、「史的唯物論」はやがてその権威を失っていく。そうしたなかで注目されたのが『経済学・哲学草稿』(Ökonomisch-philosophischen Manuskripte, 1844)や『ドイツ・イデオロギー』(Die deutsche Ideologie, 1845-1846)といったマルクスの数々の草稿や初期の著作であり(マルクス 1964、マルクス/エンゲルス 2002)、とりわけそこで展開されていた“人間論”である。本書ではこうした立場を「第二次マルクス主義」と呼んでいるが、その理論的支柱のひとつとなったのが、本書でも度々言及している「疎外論」である(「疎外論」については、【第二章:注15】、および詳しくは【補論二】を参照)。その後日本のマルクス主義哲学は、ソ連などの共産主義国家の失敗が国家社会主義、すなわち「自由な個性」を蔑ろにした全体主義に起因するとの認識から、疎外状態からの回復と「自由な個性」の開花を両面的に可能とする理論の展開を希求するようになっていく。そしてそこから注目されるようになったのが、後述する「アソシエーション論」である。例えば田畑稔は『ドイツ・イデオロギー』を紐解きながら次のように述べている。「「諸個人の連合化」としての未来社会は、一方では、諸個人から自立化した社会的諸力(資本や公権力)を諸個人自身のコントロールのもとに服従させる社会形態として構想されているが、同時に他方では、そのもとで人類史上初めて、諸個人の「個人性」が本格展開する社会形態としても構想されている。未来社会は「アソシエーション」として、つまり「個人性」の本格展開にもとづく「共同性」の自覚的形成として、構想されるべきであって、たんに「共同体」「共同社会」「共同性」の回復というように無限定なものと了解されてはならない」(田畑 1994:7、傍点は筆者による)。とはいえアソシーションの概念そのものが、古くは『共産党宣言』(Manifest der Kommunistischen Partei, 1848)に描かれた次の言葉、「階級と階級対立のうえに立つ旧ブルジョア社会に代わって、各々の自由な発展が、万人の自由な発展の条件であるような一つの結合社会(eine Assoziation)があらわれる」(マルクス/エンゲルス 1960:496、Marx/Engels 1959:482、傍点は筆者)を原型としていることは明白だろう。【注24】も参照のこと。
(5)『哲学中辞典』(2016)項目「共同性」を参照。
(6)アレント(1994)は、人間の実践のうち、生命維持に結びつく循環的な「労働(labor)」や、人工物を世界に創出する「仕事(work)」よりも、公共世界(共通世界)において自らが「唯一性」を帯びた存在として他者の前に現れる「活動(action)」こそが、人間存在のリアリティにおいて重要であると述べた。この主張の背景には、全体主義がもたらす画一性から、人間の「唯一性」や「多数性」を防衛しなければならないとする強い警鐘が込められている。こうした全体主義批判の文脈は、前述のレヴィナス(1989)にも共通しており、彼の場合は、同一性の拡大としての“全体”に対して、“全体(同化)”に回収されないものとしての異質な他者――ここでは各々異なる唯一性の象徴としての「顔」(visage)が強調される――の「無限」(Infini)が対置されることになる。
(7)【第二節】で言及する北原淳の引用部分、および【注20】を参照。
(8)こうした理解の背景に、マルクスが『経済学批判要綱』(Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, 1857-1858)において描いた以下の歴史観が流れていることは明白だろう。「人格的依存関係(最初はまったく自然生的)は最初の社会形態であり、そこでは人間の生産性はごく小範囲でまた孤立した地点でだけ発展する、物的依存関係のうえにきずかれた人格的独立性は第二の大きな形態であり、そこで一般的な社会的物質代謝、普遍的な対外諸関係、全面的な欲望、そして普遍的な力能といった体制がはじめて形成される。諸個人の普遍的な発展のうえに、また諸個人の社会的力能としての彼らの共有的・社会的な生産性を従属させることのうえにきずかれた自由な個性は、第三の段階である。第二段階は第三段階の諸条件をつくりだす」(マルクス 1958:79、Marx/Engels 1983:91)。
(9)例えば元田厚生は次のように述べる。「近代的な「個」・個人は共同体から自立し、他者の人格的依存から解放されたようにみえるが、同時に他者との間の共同性を喪失し、閉鎖性のうちに存在するようになる。つまり、近代的個人の「光」・ポジは「個別性の獲得」であるが、その「影」・ネガは「共同性の喪失」である」(元田 2007:326、傍点は筆者による)。
(10)例えば前注の元田は、続けて次のようにも述べている。「一方では「共同性の喪失」という側面を否定し「共同性の回復」を志向するとはいえ、他方では「個別性の獲得」という側面を否定することなく、それを「共同性」との連一関係において、より高い次元において保存すること、これが近代のアウフヘーベン(呑み込み高めること)の意味である……いま、個人主義と共同体主義をそれぞれ個別的に取り出していえば、現状は、一方では「さらなる個人主義」、他方では「真の共同体主義」がそれぞれ必要な状況にある。しかし、両者は二律背反的な関係にあるから、両者を包摂できる概念装置が必要である。それがアソシエーションであり、「連一関係」である」(元田 2007:326-327、傍点は筆者による)。
(11)本書ではこうした論点のことを、【第十章】において改めて「約束された本来性」と呼ぶことになる。それは、この世界には未だ現実には現れていないものの、未来において実現することが約束された「本来の人間」なるものが存在するという形而上学的・認識論的前提であり、西洋近代哲学を貫くきわめて重要な人間観であると言える。後述する「~への自由」や「積極的自由」の概念もまた、この論点と密接に関わっていると言えるだろう(【注40】も参照のこと)。
(12)「疎外論」および「物象化論」については【第二章:注15】、および詳しくは【補論二】を参照。
(13)例えば現代社会においては、「交換/契約関係」とは異なる関係、例えば同じ集合住宅の住人の間であったとしても、「共同行為」は容易に成立しない。現代社会においてアトム化、孤立化が生じているのだとすれば、その主因は「交換/契約関係」が支配的になったことによって人間本性が“歪曲”されたことにあるのではなく、〈社会的装置〉への依存によって人間の〈生〉が「自己完結」可能となったことにある、というのが本書の立場であった。同様に本書では、われわれの社会でエゴイズムや利己主義の蔓延として見えているものは、実際には人々の自発的かつ倫理的な行為であるところの「不介入の倫理」がもたらした結果であると理解される。
(14)デュルケム(1989)は、前近代的社会では、没個性的で同質な人々が「集合意識」によって結合する(機械的連帯)のに対して、近代的社会では、個性的で差異性を含む人々が分業によって結合する(有機的連帯)とした。テンニエス(1957)は、前近代的社会では、地縁、血縁、友情等が連帯の契機となり(本質意志)、近代社会では契約のように、観念的、人為的な物事が連帯の契機となる(選択意志)とした。
(15)北原(1996:47-50)。なお、大塚がここで目指したのは、マルクスが『経済学批判要綱』において言及した「アジア的形態」、「古典古代的形態」、「ゲルマン的形態」といった「資本制生産に先行する諸形態」(マルクス 1959)について分析を加え、そこでは共同体の発展段階に応じて、「私的な土地所有」と「私的な活動」の余地が拡大していくことを明らかにすることであった(大塚 2000)。
(16)日本語ではしばしば区別されていないが、厳密には“共同体”と訳されてきた語が他にもある。例えば大塚(2000)は、“Gemeinde”を、「原始共同態」からはじめ、前資本主義的な生産様式によって成立しているものを指す理念としての「共同体」、“Gemeinschaft”を、自然発生的な人々の結合形態を総称するものとしての「共同態」、“Gemeinwesen”を、共同を行っている現実の組織体としての「共同組織」、という形でおおよそ訳し分けているように思える。
(17)丸山(1964)。丸山にとっても「むら」=“共同体”は、「無責任の体系」へと連なる、「内部で個人の析出を許さず、決断主体の明確化や利害の露わな対決を回避する情緒的直接的=結合態」(丸山 1961:46)でしかなかった。丸山の議論についての詳しい説明は、【第九章:注48、注49】を参照のこと。
(18)「「近代的人間類型」の創出の成否如何が、少なくとも一つの不可欠な条件として、わが国の平和的再建の成否を、したがってわが国が世界史上再び国際的な名誉を回復しうるか否かを、まさしく、左右することになるだろう。……「近代的人間類型の創造」は、裏から見れば、あの「魔術からの解放」という世界史過程の最後の一歩であり、その徹底化を意味するものに他ならない」(大塚 1969:235)。戦後日本のあるべき形をめぐって、こうした丸山や大塚に共通する問題意識は、これまで「近代主義」と呼ばれてきた。【第九章:第三節】も参照のこと。
(19)ここでは踏み込まなかったが、「同一性」や「同質性」を強調する場合、実際には“共同体”(Gemeinde)に相当する英語である“コミュニティ”(community)の影響も無視はできない。というのも“community”の語源は「共通の」を意味するラテン語“communis”――英語の“common”に相当する――であり(『英語語源事典』 1989)、何らかの「共通のもの」を持つことによって結ばれた人間集団という含みを持つからである。そのためそこでは、地縁、血縁によって発生した村落組織を含みつつも、より広く地域社会や宗教団体、国民国家を含む多様な集団類型が想定されている。したがって、例えば北米では、かつて「リベラリズム‐コミュニタリアニズム論争」というものが行われたが、そこで語られる“community”もまた、“共同体”=「むら」よりもはるかに広義の概念であったと見る必要がある(ラスマッセン編 1998、菊池 2004)。
(20)北原は次のように述べている。「一般に、西洋近代になって生まれた共同体論は、利己主義的・競争社会的・功利主義的な近代社会を批判するため、近代社会が失った連帯や共同の契機を過去の村落社会に求め、「共同体」として理想化し、美化した。ところが、戦後日本の共同体論は、むしろ共同体が日本の後進性、前近代性の基礎にあると断じ、そういう共同体を否定して初めて近代社会が実現されるのだと説いた。……(しかし)大学の「近代主義」教育は1970年を境に衰退した。……共同体の評価もまた、このころから変化しはじめた。……つまり、日本の共同体論もまた、到達した近代の工業化・都市化社会の対極に、現実の村落社会を抽象化して「共同体」として理想化し、その対極にある現実の近代社会を批判する、という基本的構造を具えるにいたったからである」(北原 1996:6-11)。
(21)北原(1996:6-8、傍点は筆者による)。なお北原は、続いて次のようにも述べている。「共同体を復活させようとする人は、こういう「家」や「むら」の人間の犠牲やコストを伴わないような共同体をぜひとも構想してほしい」(北原 1996:8)。つまり北原自身も、ある面では「自由連帯の共同論」を夢見ていたと言えるのである。したがってここでの「忍従」や「悲しみ」は、なぜ多くの人々がこうした理想に夢を託そうとしたのかということを理解する手がかりともなるだろう。
(22)確かにそこには、時空間的に独立した存在としての「私」、他者に先行して存在する「私」という意味での“近代的自我”はなかっただろう。しかしそれは、一個体としての人間の意思や感情、またそうした意味での自意識や自我というものが存在しなかったということを必ずしも意味しない。
(23)「われわれの分析の結論は、自由は不可避的に循環して、必ずや新しい依存に導くということになるのだろうか。すべて第一次的な絆から自由であることは、個人を非常に孤独な孤立したものとするから、彼は不可避的に新しい束縛に逃避しなければならなくなるものだろうか。独立と自由は孤独と恐怖と同じことだろうか。……(われわれは)人間は自由でありながら孤独ではなく、批判的でありながら懐疑にみたされず、独立していながら人類の全体を構成する部分として存在できることを信じている。このような自由は、自我を実現し、自分自身であることによって獲得できる」(フロム 1965:283-284、Fromm 1994:256)。
(24)【注4】でも触れたように、日本のマルクス主義哲学は、「マルクス=レーニン主義」との決別以来、初期マルクスの“人間論”に依拠する形で、「自由な個性」を担保したまま、いかにして疎外の回復や新たな連帯を実現できるのかを希求するようになっていた。そうしたなかで登場したのが「アソシエーション論」である。例えば佐藤慶幸は“アソシエーション”について次のように述べる。「アソシエーションとは「人々が自由・対等な資格で、かつ自由意思にもとづいてボランタリー(自発的)に、ある共通目的のために結び合う非営利・非政府の民主的な協同のネットワーク型組織である」……「ボランタリー」ということの意味は、定義からも分かるように、国家と企業の論理から自由であるということである」(佐藤 2003:23、傍点は筆者による)。そして文中で述べたように、こうした理論を後押ししたのが、この頃盛んに注目され始めたボランティア団体、NGO、NPOの存在であった。こうした新しい現実のことを、ある人々は「アソシエーション革命」と呼び、またある人々は、「公共性(圏)」という名の「新しい市民社会」の出現として理解した。「公共性(圏)論」とは、とりわけJ・ハーバーマス(J. Habermas)の社会理論を下敷きとして、伝統的な「公(おおやけ)」とも、国家行政とも異なる、自由で自発的な諸個人がうみだす「言論空間」としての「公共性(圏)」に着目する議論のことを指している(ハーバーマス 1994、山口/佐藤/中島/小関編 2003、佐藤/大屋/那須/菅原編 2003)。その活動主体はアソシエーションのネットワークであり、それがここでは「ブルジョア社会」とは区別されるという意味において、「新しい市民社会」と呼ばれたのである(山口 2004)。他にも、「滅私奉公」とは異なる「活私開公」という形で新たな公共性を模索する公共哲学の試み(佐々木/金編 2001)や、アソシエーションが政府、市場、コミュニティの三極の橋渡しをすることを想定した「ソーシャル・ガバナンス」の試みなど(神野/澤井 2004)、当時は類似する数多くの議論が花開いていた。これらの議論は、〈自立した個人〉の思想との関連で言えば、まさしくそのひとつの到達点であったとも言えるだろう。
(25)例えば齋藤純一は次のように述べる。「公共性は、同化/排除の機制を不可欠とする共同体ではない。それは、価値の複数性を条件とし、共通の世界にそれぞれの仕方で関心をいだく人びとの間に生成する言説の空間である」(齋藤 2000:6、傍点は筆者による)。
(26)一連の共同体=「むら」に対するネガティブなイメージがもたらした矛盾のひとつとして、片仮名で表記される「コミュニティ」がある。この片仮名の「コミュニティ」は、「アソシエーション論」の高まりとほぼ時を同じくして、地域社会のつながりの回復や連帯が注目され、そのなかで用いられるようになった。それを人々が「共同体の再生」と呼ばずに、敢えて「コミュニティの再生」と呼ぶようになった理由は明らかだろう。この問題については、【第九章:注137】も参照のこと。
(27)90年代に理想化されたアソシエーションの展開は、すでに“頭打ち”の状態にあるようにも思える。そうした活動に参加する志向性を持った人々の大半は、すでに参加している状態にあるということである。また、NGO、NPOのための法制度が整ったのは90年代末から2000年代であったと言えるが、おそらくリーダー格になれる人間であれば、いつの時代も制度的環境が整っているかどうかとは関係なく、まさに自発的に活動を行ってきた側面があったと言えるだろう。
(28)この魔術的なレトリックと深く関わるものとしての「~への自由」と「積極的自由」の概念については、【注40】を参照のこと。
(29)自らの組織体を“アソシエーション”と呼ぶ人々は、建前としては自由と自発性を尊重していると言うかもしれない。しかしその実態は、むしろわれわれが〈共同〉や「共同行為」と呼ぶものと少しも変わらないだろう。そこには後述する「三つの条件」があり、“しがらみ”があり、“忍耐”がある。そしてそれが個人的な「利害」と結びつかないものであれば、そこにはなおさら負担を乗り越えるだけの強力な意志が不可欠となり、それは誰にでも実行できるものではないだろう。
(30)ここで【第五章:注9】において一度引いた、『資本論』(Das Kapital, 1867-1883)の有名な一節について再び目を向けてみよう。「自由の国は、窮乏や外的な合目的性に迫られて労働するということがなくなったときに、はじめて始まるのである。……社会化された人間、結合した生産者たちが、盲目的な力によって支配されるように自分たちと自然との物質代謝によって支配されることをやめて、この物質代謝を合目的に規制し自分たちの共同的規制のもとに置くということ……この国のかなたで、自己目的として認められる人間の力の発展が、真の自由の国が始まるのであるが、しかし、それはただかの必然性の国をその基礎として、その上にのみ花を開くことができるのである。労働日の短縮こそは根本条件である」(マルクス/エンゲルス 1967:1051、Marx/Engels 1964:828)。ここでの「必然性の国」(Reich der Notwendigkeit)から「自由の国」(Reich der Freiheit)への移行とは何を意味するのだろうか。それは一方では、資本制社会のもたらす必然的な生産諸関係から解放される、ということを意味しているのかもしれない。しかし“人間論”として読み替えられたマルクスからは、そこに「窮乏」や「自分たちと自然との物質代謝によって支配されること」、つまり生命活動の維持のために繰り返される循環的な労働――それはアレント的な意味での「労働」(labor)である(アレント 1994)――から解放され、労働をおのれ自身の「自己実現」として行えるようになることを指しているとも解釈できる。そうすると、「労働日の短縮」とは、そうした“必要労働”が最小限となり、人々がより多くの時間を「自己実現」のために使えることを意味するようになる。それは諸々の強制力から解き放たれた諸個人が、おのれの人生の主人公になるということ、そして「自由な個性」が全面的に展開される社会――【注4】の田畑の引用部分を想起――というものを意味するのである。
(31)「自由な個性」と共同性を止揚できると考える人々のなかでは、たとえ〈社会的装置〉が存在しなくとも、自発性と自由選択とに任せれば、多様性を反映した十全な調和が実現されるということになっている。それは裏を返せば、「誰もが恩恵を受けることだが、誰もがしたいとは思わないこと」であっても、それを自発的にやりたいと思う人間が必ず出現するため、それはそうした人々に任せておけばいいという暗黙の理解があるということでもある。しかしこうした主張が“悪”に転じるときこそ、おそらく本当の抑圧が始まるのである。つまり偽りの調和を守ろうとして、「あなたはそれをやりたいはずだ」と何者かに自発性を強要していくことが起こるのである。
(32)この問題こそ、もともと増田敬祐(2011、2015)が「共同の動機」という概念を用いて説明しようとしてきたことだと言えるだろう。ここでの増田の概念については、【第一章:第六節】を参照のこと。
(33)ここでは思考実験のために「掃除」をネガティブなものとして位置づけたが、“掃除”は本来、人間存在が自らの〈生〉を実践していくための、喜ばしく、また価値ある労働である。そしてその行為の意味や真価は、おそらくわれわれがそれを「やりたい/やりたくない」という次元で捉えている限り理解することはできないものである。
(34)わが国の小学校には「掃除当番」という制度が存在するが、実のところ、そこには〈共同〉実践の本質が凝縮されているようにも思える。しかし「自由連帯の共同論」の論理に則れば、こうした制度は、本来児童に対する「強制労働」として位置づけられてもおかしくはない。実際、ここで「掃除当番」に自発性や自由選択――「自発性の強要」ではなく本当の意味での――を求めるのであれば、この制度は「村」同様に破綻するだろう。
(35)「自由な個性」と共同性を止揚できると考える人々のなかには、おそらく人間が理性を行使し、普遍的な討議を行えば、自ずと「正義」が導かれるということ、またその結論が普遍的な「正義」である以上、全員が納得して然るべきだとの暗黙の前提があるように思える。そこでは納得に至らない構成員は、原理上は存在しないことになっている。そうした人間は、理性の行使が不十分な者として直ちに啓蒙の対象となるだろう。ここには文中で述べたような、〈共同〉に伴う影の部分が捨象されているのである。【注31】も参照のこと。
(36)もしかすると、われわれは無意識のうちに、たとえ潜在的に「利益」があったとしても、その事実を敢えて表に出さないことこそが、互いに気持ちよく〈共同〉を実践していく秘訣であると考えているのかもしれない。このことは、おそらく後に述べる〈信頼〉の原理と深く関わっている。つまり、不用意に「利益」を強調することによって、われわれはそこに「人格的な〈信頼〉がない」という誤ったメッセージが伝わることを恐れているのではないか、ということである。
(37)「牧歌主義的‐弁証法的共同論」は、同じ理由で近代経済学と相性が悪いと言える。それは近代経済学のもとでは、どれほど利他的に見える行為であっても、そこにはそれに見合う何らかの「効用」――例えば気分が満たされるといった――が得られているはずだとの一貫した認識があるからである。こうした人間観が、〈共同〉をめぐる多様な側面を捨象しているとの主張には同意できるが、同じことは「自然主義の共同論」においても言えるのである。
(38)「博愛主義」は、通常の人間に実践できるものではない。しかしだからこそ、そうした行為は宗教的価値を持ち、あるいはそうした行為の実践者が偉人として敬愛されてきたのである。
(39)「自発的な活動は、人間が自我の統一を犠牲にすることなしに、孤独の恐怖を克服する一つの道である。というのは、ひとは自我の自発的な実現において、かれ自身を新しく外界に――人間、自然、自分自身に――結びつけるから。……自由に内在する根本的な分裂――個性の誕生と孤独の苦しみ――は、人間の自発的な行為によって、より高い次元で解決される」(フロム 1965:287-288、Fromm 1994:259、傍点は筆者による)。われわれはここにも、あの魔術的なレトリックの痕跡を見いだすことができるだろう。
(40)「~への自由」や「積極的自由」と呼ばれてきた概念は、「自由連帯の共同論」の支柱となる「自由な個性」と共同性が止揚された状態を説明するための、ひとつの有力なモデルとしても理解することができる。その原型は、すでにJ・J・ルソー(J. J. Rousseau)の『社会契約論』(Du Contrat Social: ou Principes du droit politique, 1762)において見ることができるだろう。ルソーはそこで、ひとりひとりの人間の個別的な意志である「特殊意志」(volonté particulière)が、全人民の意志であるところの「一般意志」(volonté générale)との調和に至るとき、それは身勝手に振る舞える「生来の(自然的)自由」(liberté naturelle)を部分的に失う反面、より高級な「社会的(公民的)自由」(liberté civile)と「精神的(道徳的)自由」(liberté morale)を獲得できるとし、これこそが理想的な共和国の礎になると論じた。「人間がこの状態において、自然から受けた多くの利益を失ったとしても、大きな利益を取りもどし、その能力は訓練されて発達し、その思想は広がりを加え、その感情は崇高になる。……人間が社会契約によって喪失するものは、その生来の自由と、彼の心を引き、手の届くものすべてに対する無制限の権利とである。これに対して人間の獲得するものは、社会的自由と、その占有する一切の所有権とである」(ルソー 2005b:230、Rousseau 1966:55)。そしてカントは、このルソーの着想を引き継ぎ、それを「君の行為の格律が君の意志によって、あたかも普遍的自然法則となるかのように行為せよ」(カント 1976:86、Kant 2007:53)という一文に集約されるような道徳原理の次元にまで高めた。ここで格律(Maxime)とは、各々が自らに課している主観的な道徳原理――われわれに馴染み深い表現を用いれば“モットー”とも言える――を指しており、この主張に込められているのは、いわば皆が主観的な道徳原理に従いながらも、全員が常にその原理を普遍的に妥当なものになるよう努力することによって、究極的には、われわれは人間集団全体としても真に理性的で道徳的な世界に到達できるということである。われわれはこうした議論のなかに、「~への自由」や「積極的自由」の概念へと向かう西洋近代哲学の伝統を看取することができるだろう。なお、“自由”概念に対する本書の立場については、【補論二】において詳しく論じている。
(41)ここでの表現は、小熊英二による以下の一文から示唆を得ている。「自己の喜びが他者の喜びでもあり、他者の苦痛が自己の苦痛であり、自己と他者を区分する既存の境界が意味を失うような現象は、二人という単位で発生すれば「恋愛」という名称が付される。しかし、それが集団的に発生した場合の名称は定まっていない」(小熊 2002:828)。小熊はそれを“自由”とは呼んでいないが、この表現は図らずも、西洋近代哲学が追い求めてきた「~への自由」や「積極的自由」の境地を巧みに表現しているのではないだろうか。
(42)こうした人間学的な状態があるとするなら、それは「自由な個性」の弁証法としてではなく、むしろ後述する〈役割〉や〈信頼〉や〈許し〉が生みだすものだろう。しかし〈役割〉も〈信頼〉も〈許し〉も、決して万能なものではない。われわれはこうした特殊な状態を、そもそも普遍化すべきではないのである。
(43)例えば“家を建てる”といった持ち回りで行われる互恵的行為は、長期的な「共同行為」を通じてはじめて相互の「利益」が保障される。また多くの行事や儀礼は、ひとりひとりの参加者にとっては負担であるが、しばしば集団全体の維持にとって「利益」となり、結果的には個々の参加者の「利益」と結びつくことになる。こうした背景をくみ取り、価値づけるものこそが、「〈共同〉のための意味」だと言えるだろう。
(44)こうした「〈共同〉のための意味」は、〈生活世界〉のなかで、しばしば言語化困難な「利益」を表現しつつ、さまざまな形態を取りながら担保されてきた。例えば「情けは人のためならず」という格言は、「利他的行為」を定着させるための、広い意味では「〈共同〉のための意味」であったと言えるかもしれない。古来より人間が説話に託してきたもののなかには、こうした〈共同〉に関わる意味も含まれていたと考えることができる。
(45)ここでの“発話の技能”は、例えば今日のわれわれが想起する「コミュニケーション能力」よりも、いっそう多元的で具体的なものとして捉えられなければならない。ここには、自身の意思を伝えるための“物言い”のみならず、相手の真意を引き出す、説得する、共感する、仲裁する、根回しをするといった技能、さらには相手の“物言い”に対して、適切に怒り、適切に受け流すといった技能なども含まれるだろう。
(46)特定の人間への過剰な負担も、フリーライダーの出現も、長期的には〈共同〉の持続性を損なうことになる。ここでの“工夫の技能”には、例えば対立する構成員やグループが存在する場合に、双方の“顔”が立つような「説明」を考案するといった技能も含まれるだろう。