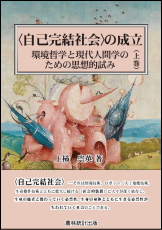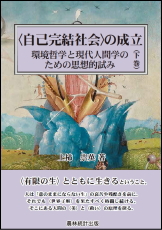用語解説
「疎外論」 【そがいろん】
- 「本書が「疎外論」と言う場合、もっぱらこのマルクスの疎外論のことを指していると考えてもらいたい。【第九章】でも触れたように、「疎外論」は60年代から70年代を中心として、「人間疎外」という言葉とともに、近代社会の病理を論じるための枠組みという形で幅広く用いられてきた。疎外概念には、何らかの外的な力によって人間本来のあり方が歪められるという含みがあり、それが産業化や大衆社会化の進んだ日本社会において、人間性やモラルの低下などをめぐる問題意識と結びつけて理解されてきたからである。」 (下巻 193)
一般的に、人間が生みだしたものでありながら、それが人間自身に対立したものとして現前することを“疎外”と呼ぶが、そこから主に近代社会におけるさまざまな病理的側面を、人間本来のあり方が歪められた結果として理解するのが「疎外論」である。
60年代以降、人間論としてのマルクスの再解釈を主軸として形成された「第二次マルクス主義」において中核的な理論となってきた(資本主義社会における交換/契約関係によって、人間と人間の関係があたかもモノとモノの関係であるかのように現前することを強調する場合は「物象化論」とも呼ばれる)。
本書の枠組みからすると、「疎外論」は〈社会的装置〉を含め、人間存在を規定する一切のものが消滅してはじめて、自由や平等を含む究極の「あるべき人間」が成立するかのように議論を組み立てている。しかし、近代社会において享受されている自由や平等が〈社会的装置〉への依存によって人為的に創出されている(〈ユーザー〉としての「自由」や「平等」)ように、ここには人間理解に対する根本的な誤りが含まれていると言える。
本書のアプローチは、確かに一方で〈関係性の病理〉、〈生の混乱〉、「〈生〉の不可視化」、「〈生活世界〉の空洞化」といった概念を多用するため、「疎外論」の延長線上にあるように見えるかもしれない。しかし「疎外論」が“病理”や“歪み”の先に見ているのが「あるべき人間(社会)」であるのに対して、本書が見ているのは、人間である限り逃れられない〈有限の生〉の諸側面であるという点は大きく異なっている(前者は理念を問題にしており、後者は事実を問題にしている)。
また、本書は〈自己完結社会〉の成立を批判的に捉えるものの、存在様式を変容させ続ける人間の営み自体は否定していない。
そこにあるのは普遍的かつ不変的な(あるべき)人間(社会)の姿ではなく、それぞれの時代に、それぞれの時代を生きる人々が行ってきた決断の帰結である。そしてわれわれは、それを正確に予見することもコントロールすることもできない(「〈有限の生〉の第五原則」)と考えられている。