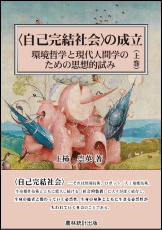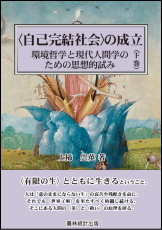『〈自己完結社会〉の成立』(下巻)
【第九章】〈自己完結社会〉の成立と〈生活世界〉の構造転換
(6)〈自己完結社会〉の成立
最後に見ていく「第五期」は、「第四期」以降の期間(2010年‐)、すなわち2020年基準で言えば、われわれが生きる“現在”である。ここで生じている数々の事態が何を意味するのか、また後にわれわれに何をもたらすことになるのか、そのことはまだ誰にも分からない。
例えば「第四期」に衰退した日本経済は、「第五期」に至って好転したと言えるのだろうか。
統計資料をもとに「アベノミクス」の成果を主張するものもいれば、それが見せかけの砂上の楼閣に過ぎないというものもいるだろう(167)。政権交代を遂げた民主党政権が3年あまりで瓦解して以来、野党の支持率は低迷し、自民党による一強体制はかえって盤石になったようにも見える(168)。
この10年、国際社会の枠組みもまた変容した。この一文を執筆している2019年時点においても、「アラブの春」の帰結として出現したイスラム国(IS)(169)、そのあおりを受けた移民問題(170)、グローバル化に逆行する一国主義の台頭(171)、そして東アジアのパワーバランスと安全保障体制の揺らぎなど(172)、「第四期」には考えられなかった事態が次々に浮上している――そして読者が本書を手に取る頃には、ここで記した“現在”もまた、新たな想定外によって塗りつぶされることになるだろう――。
加えて目を惹くのは、科学技術がもたらした新しい現実である。われわれは【第一章】において、情報技術、ロボット/人工知能技術、生命操作技術が導く未来について、すでに十分見てきたはずである(173) 。
例えばこの10年において、情報機器は驚くほど小型化し、AR、VR、IoTのほか、日々大量のビッグデータが蓄積、分析されるようになった。またディープ・ラーニングによって人工知能技術は新たな段階を迎え、自動運転から芸術、医療に至るまで幅広い応用が期待されている。
そして生命操作技術で言えば、農業/畜産の枠を超えて、2018年にはゲノム編集を施された最初の人類が誕生したとも言われている(174)。
他方で思想史的な文脈から言えば、「第五期」を代表するような新しい思想の形跡は、少なくとも筆者の実感では未だ見あたらない。社会的現実がことごとく変質したにもかかわらず、そこには依然として、現実と向き合うための意味や言葉が欠落しているように思えるのである。
驚くべきことに、多文化共生や国際平和の理念が揺らいでいくなかで、一時は「第二期」の政治的対抗軸が復活した様相さえ垣間見ることができた(175)。おそらく人文科学の主流は、いまなお「第三期」に形作られた、「存在論的抑圧」からの解放と「自由な個性の全面的な展開」とをめぐる論点に終始しており、イデオロギーや権力構造の可視化、あるいはマイノリティの権利擁護に注力している。
「ポストモダン論」について言えば、サブカルチャーの分析として一世を風靡することはあったが(176)、時代の分析に関して言えば、いまなお「大きな物語」の解体を前提とした「接続」や「切断」の問題を脱しきれずにいるだろう(177)。
「第四期」に隆盛した「アソシエーション」や「コミュニティ」についても、一定の広がりは見せたものの、その後はすでに頭打ちの段階を迎えているように思える(178)。要するにわれわれはいま、思想的な空白地帯にいるのである(179)。
〈生活世界〉の実態についてはどうだろう。われわれはそこで、まさに〈自己完結社会〉が明確な形で台頭していく姿を目の当たりにしていると言えるのかもしれない。実際、現代科学技術を背景として、〈社会的装置〉が提供してくれる財、サービス、情報の質はますます向上し、われわれの暮らしは絶え間なく高速で、便利で、快適なものへと移行し続けている。
それはまさに「〈ユーザー〉としての生」の全面的な展開であり、〈社会的装置〉がもたらす「自由」と「平等」がかつてないほどに拡大した社会の実現に他ならない。
しかしそうした時代にあって、心の病の日常化、高齢化する引きこもり、生涯未婚率の増大、孤独死の蔓延といった事態が語られるようになっている(180)。そしていつしか人々は、そうした社会のことを「無縁社会」とも呼ぶだろう(181)。
とはいえわれわれは、一連の事態を単なる“関係性の希薄化”以上のものとして理解しなければならない。なぜならわれわれが生きているのは、すでに他者との間に〈関係性〉を構築すること自体が多大なリスクとして感受される時代であるからである(182)。
例えばなぜ、あれほど監視カメラを忌み嫌った人々が、いまではそれに囲まれた暮らしをむしろ望んでいるのだろうか。それはいまを生きる人々が、生活空間に侵入してくる〈社会的装置〉の影響よりも、他者との偶発的な接触がもたらす不測の事態をはるかに恐れているからである。
いまやわれわれは、他者とのつながりを求める感情よりも、それによって自身の私的な時間、私的な空間が脅かされることの方をはるかに気にして生きている。それはかつて亀山純生が「孤人主義」と呼んだもの(183)、あるいは広井良典が「自分自身に引きこもる」と表現しようとしたものが(184)、確かな現実になったものだと言えるだろう。
こうした事態を反映するものとして、われわれは【第八章】において「不介入の倫理」という概念を導入してきた。そしてそれは、人々が自身の〈生〉にかかる全責任を自ら負うことの代償として、互いの〈生〉に介入することを積極的に拒絶しあう倫理のことを指していた。
人々はいまや、個人的な身勝手さからではなく、〈関係性〉がリスクや負担となることを熟知するがゆえに、つまり互いへの配慮という形で「不介入」を選択しているのである。
すでに見たように、〈自己完結社会〉においては、人々は〈社会的装置〉への接続を必要とするが、その通路さえ確保できれば、生身の〈関係性〉を本質的には必要としていない。そして「経済活動」や「情報世界」といった〈社会的装置〉の文脈上の〈関係性〉ならまだしも、一度そこから外れてしまうと、途端に〈間柄〉に窮してしまい、〈関係性〉の負担に耐えられなくなるのである。
われわれはここで徹底した「不介入」の行使によって、いわば〈関係性〉そのものの成立を回避させているのであり、不用意に〈共同〉が出現することを抑制しようとしているのである。
こうした「不介入」という戦略は、例えば「第四期」の人々が、誰からも「見られていない」ことを恐れ、執拗なまでに誰かと“つながる”ことを求めていたことからすれば、いささか奇妙に見えるかもしれない。
しかし、ここでは全社会的な関係性の希薄化とは裏腹に、人々自身の肌感覚としては、むしろ“つながる”こと、あるいは“つながってしまう”ことがもたらす抑圧こそが、「生きづらさ」として感受されるという、ある種の逆転現象が生じているのである(185)。
こうした事態を先取りしていたのは、おそらく「第四期」の末期において、「承認不安」と関連づけて論じられた学校現場の問題である。例えば土井隆義は、若者たちが互いに傷つき、傷つけることに全神経をとがらせる「優しい関係」に終始しており、彼らが携帯電話を手放せないのは、それが彼らにとって仲間内での自身の立ち位置を確認する「社会的GPS」としての機能を果たしているからだと指摘した(186)。
また山竹伸二は、社会や家庭のなかで十全な承認を得られなくなった若者たちが、不安定な仲間内に過剰な承認を求め、その結果互いの顔色を絶えず窺う「空虚な承認ゲーム」に陥っていると述べた(187)。
これらが物語っているのは、新時代の〈ユーザー〉たちにとって、数少ない「意味のあるもの」であったはずの「島宇宙」の内側でさえも、すでに心休まる空間ではなくなりつつあったということである。
だが問題の本質は、彼らが感じる抑圧の向こう側にあるだろう(188)。
というのも「〈ユーザー〉としての生」が全面化した世界においては、もはや“学校”とは、根源的な「生きる」理由から浮遊した人々が、劣位の人間だと思われることを恐れるばかりに、その場しのぎの〈共同〉をひたすら強制される場所、あるいは〈共同〉に対する理解も作法も未熟な人々が――〈共同〉の技能を教え、諭し、失敗を克服していく機構を欠いた状態で――クラスメートという中身のない〈間柄〉のなかに闇雲に放り込まれる場所と化しているからである。
そこでは当然、〈関係性〉や〈共同〉の負担が異常な形で突出する。そしてだからこそ、彼らは「スクールカースト」によって教室を序列化し、自ら生みだした「キャラ」という名の即席の〈間柄〉に同化しようとする(189)。それらは、歪ではあるが強力な〈間柄規定〉を伴っており、そうすることで、彼らはいわば揺らいだ「島宇宙」を安定化させようと試みているのである(190)。
こうした事態は、「情報世界」の内部においても見られる。かつて「第四期」の初頭、インターネットの黎明期においては、自室にいながら無数の情報にアクセスでき、誰もが情報の発信者となって遠くの人々と交流できることそのものが新しかった(191)。しかし今日の「情報世界」は、かつてとは比較にならないほどに肥大化している。
例えば今日のウェブページは、絶え間なく関連情報を吐きだし続け、われわれはすでに、見たくも知りたくもない情報を低意識状態のまま摂取し続ける「中毒患者」のようでさえあるだろう。とりわけ重要なのは、「Twitter」、「Facebook」、「Line」、「Instagram」といった高度なSNSが登場し、それが人間関係を支える基幹的な「インフラ」となったことである(192)。
われわれはすでに「リアル世界」と「情報世界」の間で“二重のアイデンティティ”を複雑に同期させ、いまや日常的に接する相手でさえ、SNS抜きで〈関係性〉を維持することが難しくなっている。「不介入」によって「リアル世界」が希薄化していく分、「情報世界」のなかでの“私”は、ますますその重みを増していくだろう。
ところが「情報世界」が持つ特有の構造によって、ここでは「リアル世界」とはまったく逆に、人々はどこまでも感情的になり、どこまでも不用意に互いに介入しあうことになる(193)。
例えば“コメント”や“リプライ”を行う局面において、われわれは対面する人間には決して口にできないような嫌みや罵りや嘲りの言葉を、いとも簡単に吐きだしてしまう。さらには自らの思う「正義」に反する人々を探しだしては、徒党を組んで「抹殺」しようとしているだろう。
その光景は、まさしく旧時代の人々が恐れていた“世間”の持つおぞましき側面そのものである。驚くべきことにわれわれは、「リアル世界」で失われたはずの“世間”を、今度はよりいっそう毒々しい形で、「情報世界」のなかに復活させているのである(194)。
そうしたなかで、おそらくわれわれは「〈共同〉のための作法や知恵」と言える最後のものを失った。それは、〈許し〉の解体である。
われわれはいまや、他人の失敗も、そして自身の失敗でさえも受け入れることができなくなっている。ここでは、誰もが他者から許されることを信じていないために、誰もが他者を許すことができない。そして誰もが他者を許さないために、誰もが他者から許されることを信じられずにいる。
このことは、「リアル世界」においても同じだろう。実際われわれは、「不介入の倫理」を徹底させようとするあまり、その違反者たちを発見しては責め立てている。そして自身もその規定に違反してはいないかと、日々異常なほどに気にかけながら生きているのである(195)。
だからだろうか。人々はどこかで常に余裕がなく、皆がぎすぎすとした感情を抱えて生きている。そして「二つの世界」のあちらこちらにおいて、人間存在そのものに対する底知れぬ不安、恐れ、憎しみばかりが無数に蓄積されているのである。
さて、一連の変化から、われわれは何を読み取ることができるのだろうか。それは、われわれが〈ユーザー〉として自立しているからこそ、かえって〈関係性〉の負担が増大し、他者がいっそう抑圧的なものとして感受されるということ、さらにはその反作用として、皆が「不介入」を行使するからこそ、よりいっそう〈関係性〉の負担が増大するという悪循環である。
そして問題の本質は、抑圧の背後に隠された一連の〈共同〉の不可能性と、それでもなおわれわれは〈共同〉を完全に避けることができないという現実との矛盾にこそある。
【第八章】では、この「不介入」という戦略自体が、いまや多くの綻びに直面していることついて見てきただろう。われわれは人間である限り、望まぬ〈共同〉や、望まぬ〈間柄〉を引き受けなければならないときもあれば、仮面を外して「〈我‐汝〉の構造」を通じて向き合わなければならないときもある。
その一切を回避しようとするからこそ、「不介入」はかえってわれわれに多大な苦しみをもたらすだろう。いずれにしてもわれわれは、こうして「不介入」に励みながら、その試みがいつ破綻しやしないかと日々怯えて暮らしているのである。
それでは「第四期」に見られた、あの「かけがえのないこの私」をめぐる葛藤、そして存在の浮遊性がもたらす、あの「諦め」の感情についてはどうなったのだろうか。
まず後者について言えば、夢や個性に邁進して挫折した年長世代をよく見て育った新しい世代は、確かに安易に希望を語ろうとはしないだろう。しかし彼らは、どこか年長世代よりも深い「諦め」によって、むしろ最初からすべてを「諦める」ことにしているだけに過ぎないようにも見える。
例えば彼らが「価値観など皆それぞれ」と吐き捨てるとき、他者とは分かり合えない存在ではなく、すでに分かり合えるはずのない存在となっているだろう。
彼らが恐れるのは、努力をしたからこその失敗という結末、何かを信じたからこその裏切りという結末であって、だからこそ彼らは、自己責任で対処できる範囲を精査し、そこそこ満足のいく現状だけを必死に守ろうとしているようにも見えるのである(196)。
そしておそらく「第五期」の人々もまた、理想と現実との間で引き裂かれている。人々が信じることができるのは、おそらく自分だけの時間と空間、言ってみれば肥大化した「自分だけの世界」だけである。そしてそれは、他者という脅威から逃れることのできる、「かけがえのないこの私」の“聖域”に他ならない。
こうした人々にとって、人生とは、本質的に「この私」で始まり「この私」で終わるものである。他の誰のものでもない、「この私」だけのものであって、それゆえ「この私」によって「意のままになる」べきはずのものである(197)。これこそが人々にとっての「自己実現」の形であり、それは皮肉にも、自由選択と自己決定を至高とする〈自立した個人〉の究極の形でもあるだろう。
しかしどれだけ「自分だけの世界」が充実しようと、おそらく人々は、存在に揺らぐ自身の渇きが、「自分だけの世界」では決して満たされないということを理解してもいる。
それでも「この私」の王国において、許容されうるのは「この私」にとって都合の良いものだけに限られる。「この私」の物語において存在して良い人物は、言ってみれば「意のままになる他者」だけなのである(198)。
そしてだからこそ、人々は深く葛藤する。彼らはいまなお、誰かにしっかりと側にいてほしいと願ってしまうし、自分のことを、誰かに深く理解してほしいと願ってしまう。それでも「不介入」の楽園に慣れ過ぎてしまった人々は、「自分だけの世界」を脅かすわずかな傷にも耐えられない(199)。
〈共同〉が求める負担など、いったい誰が背負えるなどと思えるのだろうか。そうして関わりたいときに関わってもらえず、関わりたくないときに関わりを強いられるといって、〈関係性〉に意味を求めること自体を、次第に「諦め」るようになるのである。
先にわれわれは、生まれながらに〈ユーザー〉となった人々、それゆえ〈存在の連なり〉から切断された人々のことを〈漂流人〉と呼んできた。かつて〈郊外〉で育った〈旅人〉の子どもたちは、成長して〈漂流人〉となった。
「第五期」とは、そうした〈漂流人〉たちが成熟して壮年期を迎えていく時代、さらに言えば〈漂流人〉の第一世代によって産み育てられた、〈漂流人〉の第二世代が成長していく時代でもあると言える(200)。あの〈郊外〉の時代のはじまりから数十年の時を経て、われわれはそこに何を見いだすことになるのだろうか。
例えばわれわれは、そこで〈社会的装置〉に付属する〈郊外〉であっても、年月とともに人間存在の〈生〉の履歴が、つまり〈生〉を紡ごうと人々が重ねてきた格闘の記憶、そして〈共同〉の記憶が芽生えていることを知るだろう(201)。
だが、それはかりそめのものではないだろうか。われわれの目に映るのは、整然と並ぶその人工物の塊が、一斉に高齢化し、一斉に老朽化していく姿である。その姿が物語っているのは、〈郊外〉が結局は一世代きりの使い捨ての街であったという単純な事実である。
したがってかつての〈郊外〉は、その記憶を継承することなくいずれは消滅する。そしておそらくその場所に、あるいはまたどこか別の場所に、記憶を持たない新たな〈郊外〉が再び誕生することになるだろう。こうして〈漂流人〉たちが、再び生産されていくのである。
【第九章】(7)“時代”と人間の〈生〉 へ進む
【下巻】目次 へ戻る
(167)「アベノミクス」は、もともと2012年に成立した安倍政権が就任直後に打ちだした、「大胆な金融政策」、「機動的な財政運営」、「民間投資を喚起する成長戦略」からなる政策課題(「三本の矢」)を指す用語であったが、今日では広義に安倍政権の政策全般を指すものとして用いられている。2010年代末の安倍政権の政策を俯瞰してみると、「希望出生率1.8」、「介護離職ゼロ」、「人づくり革命(教育無償化)」、「働き方改革」など、行政サービスの拡充を進めている側面があり、それは小泉政権時代の「小さな政府」路線とは明らかに様相が異なっている。また同じ文脈から、逆に小泉政権が取り組んだ財政再建からは大きく後退しているとも言えるだろう(2019年には消費税が10%に引き上げられたが、それはもともと2015年に行う予定のものであった)。さらに「マイナス金利」や「異次元の量的・質的緩和」といったように、経済政策が極端な金融政策に依拠したものであるとの批判があり、評価を行うには少なくとも後10年が必要だろうと思われる。詳しくは小峰(2019)を参照。
(168)民主党は2009年に政権交代を実現したが、まもなく政権運営に行き詰まり、わずか3年で再び政権を自民党に明け渡すことになった。その後野党は、民進党(2016年結党)、希望の党(2017年結党)といった形で繰り返しマニフェスト選挙を試みてきたが、結局一度も政権交代を実現することはできなかった。その背景には、統一野党が「反自民」以上の政治的な対抗軸を打ちだせないということもあるだろう。実際、経済政策の面から言えば、安倍政権は小泉政権に比べると相対的にリベラル寄りであり、その分野党勢力にとっては、経済理念に基づく対抗軸を示すことが難しくなっている(小泉政権時代とは異なり、両者の経済理念には本質的な差異がなくなりつつある)。立憲民主党(2017年結党)が「集団的自衛権の容認反対」や「憲法改正反対」といった形で、執拗に経済以外の理念を持ちだすのも、筆者にはかつての社会党が、対抗軸を示そうとして「平和主義」を強調しなければならなかったことと重なって見える。もっとも世界情勢の変化によって、伝統的な「平和主義」を掲げることはますます困難となるだろう(しかも政治改革後の野党勢力は、旧民主党のように自民党造反者と旧野党の混成体であり、経済政策以外の理念を強調すればするほどに共闘が困難となる)。そうすると、野党勢力はますます不健全にスキャンダルに頼らざるをえなくなる。しかしスキャンダルだけでは政権担当能力を示すことにはならず、結局支持をえられることもないだろう。野党が健全さを喪失すれば、与党もまた健全さを失っていく。日本の政界はこうした悪循環に陥っているように思える。
(169)2010年末のチュニジアから始まったイスラム圏での民主化運動は、一部の国においては深刻な内戦をもたらした。とりわけシリアにおいては、周辺国や大国がそれぞれに政府側と反政府組織側を支援したことから、泥沼の争いへと発展していった。隣国イラクにおいては、イラク戦争後の新政府に国土全域を統治できる十分な能力がなかった。そうしたなかで、シリアとイラクにまたがる広範囲を制圧した「イスラム国」は、世界各地のイスラム原理組織と連携し、多くのテロ事件を発生させるようになっていた。詳しくは長谷川/金子編(2019)、ボニファス(2019)を参照。
(170)欧州における「移民/難民問題」といえば、かつては旧東側世界からの移民を指すものであったが、この時期には「アラブの春」やシリア内戦のあおりを受けて、イスラム世界からの移民/難民が急増していた。とりわけ2015年には、100万人近い難民が域外から欧州に押し寄せたと言われている。欧州では当初、EUを中心に積極的な受け入れがなされていたものの、その後、治安の悪化をはじめとしたさまざまな矛盾、限界が露呈するようになり、結果として、各国には移民/難民の排斥を掲げた政治勢力が伸張することになった。長谷川/金子編(2019)を参照。
(171)「一国主義」という言葉からは、2016年に生じた二つの事態が連想される。ひとつは米国で成立したトランプ政権であり、もうひとつは国民投票によって決定した英国によるEU離脱問題である。確かに当時、民主主義の守護者を自認してきたはずの知識層が、民主的な手続きによって成立した結果をこれほど攻撃するのは奇妙であったし、あれほどグローバリズムを糾弾してきた新自由主義への批判者たちが、方向性としては「反グローバリズム」とも言える二つの事態に落胆したのも奇妙なことであった。しかし両者には似た側面が他にもある。例えば両者が、移民/難民の流入に伴う社会的リスクに直面して、それを全地球的な課題として負担を分け合う“包摂”という道ではなく、壁や封鎖といった“排除”の道によって解決しようとしたこともそうであった。要するにエリートたちが落胆したのは、おそらく現実がもたらす要請や、人々の行った合法的な選択が、【序論:注3】で述べた、コスモポリタニズム(世界主義)や多文化共生といった長年の理想を瓦解させるものだったからなのである。
(172)ここで重要なのは、台頭する中国と、これまで一強の座にあった米国との対立である。中国は今世紀に入って爆発的な経済成長を遂げ、2010年代の後半には、自らが主導する国際秩序の建設を明確に打ちだすようになっていった。なかでも指導部が掲げる「中華民族の偉大なる復興」には、軍拡や海洋進出、領土拡張などの要素が含まれており、東シナ海には制海権を狙う「(第一)列島線」が、南シナ海には領有権を主張する「九段線」がそれぞれ大きくせりだす形で敷かれ、日本を含む周辺国との間で緊張を高める結果となっている。ところがそうした状況下にもかかわらず、トランプ政権の同盟国への接し方は「世界の警察」というよりもビジネスパートナーに近く、利益に見合わなければ米軍の撤退をも辞さない構えを見せている。「米軍基地は米国の世界戦略のためのものであり、日本はそれに巻き込まれている側に過ぎない」とする「第二期」以来の論理は、おそらくすでに通用しない。安全保障を全面的に米軍に依存してきた日本社会は、まさに試練のときを迎えていると言えるだろう。長谷川/金子編(2019)、ボニファス(2019)も参照。
(173)現代科学技術の詳細については【第一章】で触れているので、ここでは改めて言及しない。
(174)詳しくは【第一章:注31】を参照のこと。
(175)例えば2015年に、いわゆる「安保法案」――正確には、武力攻撃事態法や自衛隊法など関連10法の改正案を束ねた「平和安全法制整備法案」と、紛争下の他国軍への後方支援を恒常的に可能とする「国際平和支援法案」からなる――が制定された際、「集団的自衛権」の容認やその根拠となる「存立危機事態」などをめぐって多くの議論が喚起された。その法案の是非はともかくとして、ここで注目しておきたいのは、このときマスメディアを中心に繰り広げられた“フレーム”である。例えば、同法が平和憲法を毀損し、日本が他国の戦争に巻き込まれるリスクを高めているとする批判の形、採決を「強行」する与党に対して身を挺してそれを阻止しようとする英雄的な野党像、音楽やデモ行進など非暴力的な手段を用いて反対を訴える若者たちの姿などは、「第二期」の「六〇年安保闘争」の構図と驚くほど一致しており、それはまさしく「現実を盾に戦後的理想を毀損しようとする国家権力の横暴と、そうした権力に立ち向かい、立場を超えて自発的に連帯する良心的な市民の姿」の再演とも言えるものであった。
(176)例えば東浩紀は、「第四期」の段階でサブカルチャーの分析を通じて、そこに現れる新しいリアリティの特徴を「データベース消費」と呼び、そこからポストモダン状態における人間様式を「動物化」と表現していた。「「動物になる」とは、そのような間主体的な構造が消え、各人がそれぞれ欠乏――満足の回路を閉じてしまう状態の到来を意味する。……マニュアル化され、メディア化され、流通管理が行き届いた現在の消費社会においては、消費者のニーズは、できるだけ他者の介在なしに、瞬時に機械的に満たすように日々改良が積み重ねられている。……ポストモダンの人間は、「意味」への渇望を社交性を通じては満たすことができず、むしろ動物的な欲求に還元することで孤独に満たしている。そこではもはや、小さな物語と大きな非物語のあいだにいかなる繋がりもなく、世界全体はただ即物的に、だれの生にも意味を与えることなく漂っている」(東 2001:127、140)。こうした主張には、〈自己完結社会〉をめぐる本書の分析にも結びつく重要な視点が含まれていたと言えるだろう。とはいえ、その後継者たちは――例えば宇野常寛(2011a)のように、それをサブカルチャー分析という形で継承しつつ、時代分析につないだものも見られたが――多くの場合、サブカルチャーを分析すること自体に主眼が置かれ、時代分析という形では、十分な議論を展開することができなかったように思える。
(177)「私たちは、偶然的な情報の有限化を、意志的な選択(硬直化)と管理社会の双方から私たちを逃走させてくれる原理として「善用」するしかない。モダンでハードな主体性からも、ポストモダンでソフトな管理からも逃れる中間地帯、いや、中間痴態を肯定するのである。……文化的な非意味的接続の希望から出発し、その非意味的切断も必要であると但し書きを付すのがポストモダン論であった。逆に、非意味的切断の不可避さから出発し、非意味的接続を、部分的にしか可能ではないという前提のもとで試行錯誤することが、ポストポストモダンの課題である」(千葉 2013:37-38、傍点はママ)。もっとも本書の立場から言えば、われわれに必要なのはあくまで「意味的な接続」であって、その基盤となるのは【第十章】で見ていく〈有限の生〉との対峙、とりわけ「絶対的普遍主義」とは異なる態度で構築されうる「人間的〈生〉」をめぐる作法や知恵といったことになるだろう。【注185】も参照のこと。
(178)NPOやボランティア活動はすでに社会内部に深く浸透しており、生活支援や災害支援など、現代社会はすでにそうした組織の協力なしには成り立たなくなっている。しかしそれは「第四期」に語られた「新しい市民社会」の姿、アソシエーションネットワークによる新しいガバナンスの台頭とは程遠いものであった。
(179)もちろんこのように主張することは、ある種の語弊があると言えるかもしれない。例えば青土社が刊行している『現代思想』を紐解いてみても――とりわけ筆者が本書の底本原稿の執筆に注力していた2015年から2020年にかけて――「人新世」(anthropocene)、「加速主義」(accelerationism)、「新しい実在論」、「新しい唯物論」といった海外からの議論の紹介が、とめどなく続けられてきたからである。しかし“舶来品”として導入された一連の言説が、かつての「第二次マルクス主義」や「ポストモダン論」のように、時代を代表する思想的趨勢として確固たるものを残しうるのか、それとも単なる一次的な流行として終わってしまうのか、筆者は本書の出版時点においても、確信を持って答えることができずにいる。確かなことは、5年後には、また何者かが目新しい言説を海外から輸入することになり、10年後には、また10年後を反映した、目新しい舶来品が出回るだろうということだけである。とはいえ現時点において、先の諸言説が流行していることは事実であり、とりわけ「人新世」や「加速主義」といった主題は、確かに現代科学技術と人間存在の生き方、あり方を問題としてきた本書の内容とも深く関わる部分がある。そのため、こうした言説と本書の接点については、いずれは別の機会を設けて論じることにしたい。
(180)厚生労働省(2018)によれば、「気分(感情)障害(躁うつ病を含む)」に相当する外来の患者数は、2017年の時点で124.6万人であり、2002年の68.5万人から大幅に増加している。また高齢化する引きこもりについては、近年「8050問題」――子が50代、扶養していた両親が80代を迎え、経済的困窮や社会的孤立から親子共倒れの危険性がある――とも呼ばれている(川北 2019)。再び厚生労働省(2018)によれば、生涯未婚率(50歳時の未婚の割合)は、1985年の時点で男性3.9%、女性4.3%だったものが、その後は男性25%前後、女性15%前後にまで急増しており、次第に漸増に移行するものの、2040年には男性の約3割、女性の約2割にまで上昇することが推計されている(この問題については山田(2014)も参照)。NHKの取材班は、誰にも知られることなく死亡した人々の実態を、行政記録として残される「行旅死亡人」――住所氏名などが不詳で、遺体の引き取り手もない死亡人のこと――を手がかりに、2010年の段階で全国3万2000人に達していると推計した(NHK「無縁社会プロジェクト」取材班編 2010)。
(181)「無縁社会」という用語は、2010年にNHKで放送された『無縁社会――“無縁死”3万2000人の衝撃』を通じて定着したものだと思われるが、それはリアルな関係性が縮小していくなかで、誰もが孤独を抱えながら、一人きりで死んでいく未来と隣り合わせに生きている現実を的確に象徴しうる言葉であった。
(182)ここで再び【はじめに】の冒頭で取りあげた、住人同士の挨拶を禁止することを決定したマンションについての新聞投稿を想起してもらいたい。
(183)「だから、かつてのように単純なアトム的個人の批判の立場から、ただ“関係性”の必要を言うのは的外れである。……それは関係性の中の“孤人主義”であり、内面ではすでに引き籠もりである。だが、孤立の中では生きた“人間力”は育たず、社会が個々に求める“人間力”(自己性、身体力、他者関係性)は逆に抑圧となる。問題なのは、疎外回復の要をなす他者との関わりそれ自体の抑圧化である……深刻なのは、それなのに若者が生活に満足している点である。……満足の下では抑圧が現状転換のテコとはならず(“見えない抑圧”)、若者は“孤人主義”を自ら脱却しようとはしない。まさしく人間疎外の“窮極の完成”である」(亀山 2011:283-284、傍点は筆者による)。
(184)「いわば「ムラ社会」の“単位”が「農村→カイシャ・核家族→個人」という形でどんどん縮小し、あたかも個人一人ひとりが閉じたムラ社会のようになり、新たな「つながりの原理」を見出せないでいる、というのが現在の日本社会ではないだろうか」(広井 2006:5、傍点はママ)。
(185)例えば前掲の千葉雅也は言う。「もっと動けばもっと良くなると、ひとはしばしば思いがちである。ひとは動きすぎになり、多くのことに関係しすぎて身動きが取れなくなる。……動きすぎの手前に留まること。そのためには、自分が他者から部分的に切り離されてしまうに任せるのである。自分の有限性のゆえに、さまざまに偶々のタイミングで」(千葉 2013:52)。筆者はこれを、「接続」に期待する「第四期」の思想に対して、われわれの現実においては、むしろ接続過剰の状態に置かれているという、「第五期」的な肌感覚から行われた批判であると理解した。なお、千葉はこの「過剰接続」を克服する鍵として「有限性」に着目しているが、それは「享楽的こだわり」に象徴される個人的な趣味趣向の偏りのことであって(千葉 2017)、本書が【第十章】で見ていくような〈有限の生〉とはまったく異なるものだと言える。
(186)土井(2008)。
(187)山竹(2011)。
(188)筆者はこの問題を、「第三期」までの「抑圧からの解放」や「本当の私」をめぐるロジックを用いて捉えるべきではないと考えている。確かに、人が他者からの期待や、他者から付与される“ラベル”に過剰に同化してしまうとき、それらを一度相対化させ、「私の本心」がどこにあるのかを問い直していくことは、対症療法としては必要なことであるだろう。しかしここには、そうした対症療法以上のものは存在しないということもまた、忘れてはならないように思える。なぜなら人間的現実においては、抑圧の存在しない〈関係性〉も、他者から切り離された「本当の私」も存在しないこと、言い換えれば人間は、負担を伴う〈関係性〉から決して逃れられず、その宿命のなかで折り合いをつけながら生きていかねばならないからである。繰り返すように、〈間柄〉の存在そのものが忌避すべきものであるわけでは決してない。〈間柄〉の媒介がなければ、人間はその〈関係性〉の重みに耐えられないからである。問題は、それが〈間柄〉の仮面を外す余地のない極端なものとなり、過剰適応の状態を誘発している現状があることである。それは〈距離〉の概念が存在しない〈関係性〉、本書が「0か1かの〈関係性〉」と呼んだものに酷似していると言えるだろう。重要なことは、それを単なる「抑圧」と見なして排除しようとすることではなく、社会的な次元においては、古くなった〈間柄規定〉を修整していくこと、そしてわれわれが使用可能な多彩な〈間柄〉を共有し、〈距離〉を適切に測る技能を身につけていくことであるように、筆者には思えるのである。
(189)土井(2009)や斎藤(2013)によれば、「キャラ」とは「いじられキャラ」、「おたくキャラ」、「天然キャラ」といった、特定のグループ内での役割の“プロトタイプ”に相当するものであるとされている。「第四期」末の学校現場においては、コミュニケーション能力の高低が非常に強力な意味を持ち、それによって複数のグループが編成されるほか――これが「スクールカースト」を形成する――さらにはそれぞれのグループのなかで「キャラ」の振り分けが半ば強制的に行われているとされる。「大きな物語」の喪失と価値の多元化のなかで、アイデンティティという一貫性を維持することは困難であり、「キャラ」はそうした状況下において、「敢えて人格の多様面をそぎ落とし、限定的な最小限の要素で描きだされた人物像」という形で、「錯綜した不透明な人間関係を単純化し、透明化してくれる」(土井 2009:25)わけである。こうして考えると、「キャラ」がある種の〈間柄〉であることは明らかだろう。ただし、それが年月をかけて培われてきた〈間柄〉と異なるのは、それが小グループというきわめて限定的な関係性のなかにおいてのみ成立するものであること、グループ内の力学によって流動化しうる、きわめて不安定なものであること――これらは山竹(2011)が強調していた点でもある――さらに言えば、特定の「キャラ」に振り分けられると、その「キャラ」から逸脱することが許されなくなるという意味において、〈距離〉の概念が欠落した極端な〈間柄〉であることなどである。
(190)こうした経験を積み重ねたところで、人々に意味のある〈共同〉の技能や作法が涵養されることはおそらくないだろう。そこで磨かれるのは、その場を優位に切り抜けられる「コミュニケーション能力」ばかりであって、人々はかえってますます他者と関わっていくことへの猜疑心や挫折感ばかりを植えつけられる結果となるからである。ここから見えてくるのは、幼少期から経験される、こうした〈共同〉の不可能性こそ、他者を多大な抑圧として認識させ、人々をますます「不介入」へと向かわせるひとつの原動力となってきたということではないだろうか。
(191)かつての「情報世界」は、「リアル世界」のしがらみから解放される特別な空間としての意味があった。それはとりわけ、「第三期」以降の〈隠者〉たちにとっての居場所であり、そこには「リアル世界」にはない独特の連帯感さえ存在していたと言えるだろう。しかし「情報世界」が肥大化し、「リアル世界」と地続きになっていくと、かつての自由さも、連帯感も、そして〈隠者〉たちの居場所としての側面もまた失われていった。こうしたインターネットの古き良き時代については、ばるぼら(2005)、ばるぼら/さやわか(2017)を参照。
(192)今日の代表的なSNSである「Twitter」、「Facebook」は2000年代に、「Line」、「Instagram」は2010年代になって普及した。かつて日本では「Mixi」という国産SNS(2004年にサービスを開始)が普及していたが、2010年代には利用者の低迷が続き、「Facebook」もまた比較的若い世代には普及しないといったように、その構図は日々変化していると言える。木村(2012)によれば、早い段階で機能に即したSNSの使い分けが進んでおり、実名で交流を広げることを目的とする「Facebook」に対して、「Twitter」は実名/匿名を含めて、受け取り手に返答を強制することなく気軽に心情を表出できるという絶妙な“ニッチ”を占めていたという。加えて今日では、「Line」が返答を前提とした連絡用ツール――それはかつての電子メールの代替である――となり、「Instagram」が画像の投稿に特化したものとして機能していると言えるだろう。
(193)はたして人々は、ここでコメントやつぶやきを投稿した何者かが、例えば学生であったり、会社員であったり、貧しかったり、裕福だったり、闘病者だったり、独居老人だったりといったように、特定の年代に生まれ、否応なく何らかの属性や立場を背負い、固有の歴史と多様な〈関係性〉のなかで生きる一人の人間であるということを想像することはあるのだろうか。われわれはそこで、無意識のうちに、「自分だけの世界」の延長線上で他者と関わろうとしているように見える。そこでは「仲間以外は皆風景」(宮台 2000)ならぬ、「自分以外は皆風景」なのであって、だからこそあれほどの不用意な介入ができるのではないだろうか。
(194)確かに〈自立した個人〉の信奉者たちは、この「世間的なもの」こそが個人を埋没させる日本固有の悪しき機構であり、“世間からの解放”こそがわれわれの目指すべきものだと主張してきた側面がある。しかし「リアル世界」でめでたく世間が弱体化したにもかかわらず、いまや「ネット世間」なるものが誕生したのはなぜだったのだろうか。それは人々が、どこかで再び「世間的なもの」を求めていたからではなかっただろうか。というよりも、【第七章】で触れたように、人間は自身の認識や思考を相対化させるための“標準”や“尺度”というものを必要としており、その要求が、おそらく現代社会においては「ネット世間」という形で具現化したのである。
(195)このことを増田敬祐は、「環境の出来事に関わることを負いきれなくなった人間」が、律しきれない自らを罰しようとする「自罰」と、律していないと判断された他者を罰しようとする「他罰」の関係において分析している。「問題は自罰に起因する人間の不満や不平の矛先が怒りとなって他罰に向かうときである。……自分を内面的に律することが人間の「本来」の理想の姿として称揚される一方で、現実の環境を生きる存在としては、その求められる理想の人間像の前でそれを目指せば目指すほど自罰的にならざるを得ない自分を思い知らされる。自分が「本来」の「あるべき姿」に近づこうと苦労し自罰的になっているときに、自分以外の人間が自分と同じように自らを律することにおいて自罰的でなければ、その人間に対し憎悪の感情が芽生え、他罰的な怒りの矛を向けてしまう」(増田 2020b:327-328)。
(196)「第四期」と「第五期」の狭間に、古市憲寿(2011)は、この国が財政赤字や少子高齢化などの深刻な問題を抱えた「絶望的な国」であるにもかかわらず、そのなかで生きる若者たちが幸福そうに見える背景について分析した。古市がここであげているのは、例えば未来が絶望的であるほど現在を相対的に幸福だと感じる心理、未来に予想される困難の見えにくさ、現在の承認を満たしてくれるツールの多さ、といったことである。もちろん、いつの時代も積極的な人間は一定数存在しており、「第四期」には海外の職人に弟子入りしたタイプの人間は、今日では起業を行ったり、あるいは「YouTuber」になったりして活躍していると言えるだろう。しかし全体として感じ取れることは、新しい世代の人々が、“コスパ(タイパ)”を強く意識しながら、失敗のない幸福を志向し、そもそも“期待値”が低いがゆえに幸福感が高く見えるということである。
(197)筆者はここで、否応なく吉田健彦の次の言葉を思いだす。「見ることと見られること、記憶されることと記憶することの間に横たわる断絶が消失したとき、我々はただこの私だけが浮かぶ孤絶した宇宙における神となる」(吉田 2017:389)、「技術への欲望が差角として他者との交感と他者の支配を、そして他者への欲望が他者への希求と怖れを同時に内包していたのに対して、無限と永遠への欲望にはいかなる差角もない。我々にはもはや他者に由来する苦痛も制約もなく、真空をどこまでも直線運動していくだろう」(吉田 2017:403)。
(198)「自分だけの世界」を生きる人々は、だからこそ恋愛も結婚も忌避するようになる。そしてそうした人々が、子孫を残すことに意味を見いだせなくなるのも当然の帰結ではないだろうか。というよりも、たとえそれを本心では望んでいる人間であっても、早々に現実に窮してそれを「諦め」ているのである。なぜなら、それらはいずれも、「自分だけの世界」のオプションとして選択するにはあまりに負担が大きいものであること、「意のままにならない他者」と向き合うことが要請され、「自分だけの世界」を解体することによってはじめて可能となるものばかりだからである。
(199)その姿は、あたかもあまりに清潔な環境で育った人間が、それゆえ病的な潔癖症となって、わずかな汚れにも反応して取り乱してしまう姿、そして汚れの落とし方が分からないために、その場しのぎの対応を行った結果、かえって自身を苦境に追い込んでいく姿であるかのようである。
(200)〈郊外〉で育った第一世代には、多くの場合“実家”というものが存在した。確かにその実家という〈故郷〉には、〈存在の連なり〉に裏打ちされた重厚さはなかったかもしれない。それでもそこには“家庭”という、最後に残された〈共同〉の世界が存在していたとも言えるだろう。その意味ではタワーマンションの一室でさえ、ある人にとってはひとつの〈故郷〉となる。だがやがて、人々が〈郊外〉に「定住」することもなくなり、寂寞と広がる「〈郊外〉的な空間」にただただ浮遊し続ける存在となったとき、〈故郷〉の形とはどのようなものになるのだろうか。
(201)例えば金子淳(2017)は、ニュータウンであっても、開発以前の土地の歴史を掘り起こし、旧住民と新住民の記憶の交流を進めることによって、そして年月の経過とともに刻み込まれた記憶の痕跡に目を向けることによって、〈郊外〉的な浮遊性を脱構築することができると述べている。しかし人々は、それを本当に望んでいるのだろうか。〈ユーザー〉となった人々が望んでいるのは、結局コンセプト化されたハコモノの美しさではないかと筆者は思う。そしてそうした美しさは、過去に生きた人々の〈生〉の痕跡や記憶などを含めて、むしろ一連の煩わしい〈存在の連なり〉から切り離されているからこそ可能となるものだったのである。