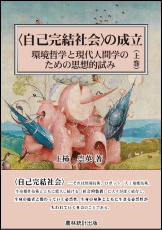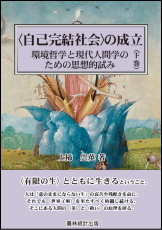『〈自己完結社会〉の成立』
【序論】――本書の構成と主要概念について
(4)本書の構成について 第3部
【第三部】「「人間的〈生〉」の分析と〈社会的装置〉」では、視点を変え、第二のアプローチである「〈生〉の分析」を用いた人間の解明を試みていく。
【第五章】「「人間的〈生〉」と「〈生〉の三契機」」では、まず「〈生〉の分析」を行うための基本的な枠組みについて整備する。われわれはここで、生活者としての人間、そして生身の人間にとっての等身大の世界である〈生活世界〉に着目しつつ、そうした場を舞台に展開される「人間的〈生〉」の構造について詳しく見ていくことにしよう。
最初に取りあげたいのは、人間存在には、時代や文化を問わず、人間である限り必ず実現しなければならない三つの事柄、「〈生〉の三契機」と呼べるものが存在するということである。
それは第一に「〈生存〉の実現」、すなわち生命体として生きる人間が必要物を確保し、そのための素材の加工や道具の製作、知識の集積などを行っていくこと、第二に「〈現実存在〉の実現」、すなわち他者とともに生きる人間が集団の一員としての自己を形成すると同時に、構成員との間で情報を共有し、信頼を構築し、集団としての意思決定や役割分担を行っていくこと、そして第三に「〈継承〉の実現」、すなわち生命体として死を迎える人間が、前世代から受け継いだものを改良しつつ、再び次世代へと引き渡していくことである。
本章では、このことを踏まえて「〈生〉の不可視化」の問題についても掘り下げていこう。それは現代社会に生きるわれわれが、現実として〈生〉に肉薄しているにもかかわらず、なぜこれほど〈生〉=「生きる」実感を得ることが困難なのかという問題である。
手がかりとなるのは、現代社会においては、「〈生〉の三契機」の実現が、主として〈社会的装置〉への“委託”という形で達成され、人々にはそれらが矮小化された形でしか経験されないということである。
われわれはここで、現代における「〈生存〉の実現」は、直接的には〈社会的装置〉に接続するための“貨幣”を調達する「経済活動」を意味すること、「〈現実存在〉の実現」は、〈社会的装置〉のもとで、自身が望んだ自己の形を具現化していく「自己実現」を意味すること、そして「〈継承〉の実現」は、将来の「経済活動」や「自己実現」のために課せられる「学校教育」を意味することについて見ていく。
そして一連の事態を「〈生活世界〉の空洞化」と呼び、こうした現代的な〈生〉のあり方を指して「〈ユーザー〉としての生」と呼ぶことにしたい。
加えて本章の後半では、われわれは「〈生〉の三契機」の起源について、とりわけそこになぜ“三つの契機”がなければならないのかという問題について考えていく。
ここではまず、〈生〉の契機において最も根源的なのは「〈生存〉の実現」であるということ、加えて人間存在にとっての〈生存〉とは、常に集団行動によって実現される「集団的〈生存〉」を意味するということについて見ていこう。
そして人間の集団性が、量的にも質的にも異常なほどに突出したものでありながら、人間の遺伝的単位は個体であること、それゆえわれわれは「“私”の〈生存〉」と「“皆”の〈生存〉」をめぐる〈根源的葛藤〉を抱えるに至ったのではないかということについて指摘することにしたい。
実はこのことは、「人間的〈生〉」の文脈から“〈社会〉の起源”を考えるうえできわめて重要な示唆を含んでいる。つまり、われわれが【第二部】において「人為的生態系」としての〈社会〉という形で見てきたものが、もともとはこの〈根源的葛藤〉を軽減させ、「集団的〈生存〉」を円滑に実現していくための仕組み、いわば「〈生〉の舞台装置」として発達してきたものだったのではないかということである。
加えてこの「〈生〉の舞台装置」としての〈社会〉という概念によって、われわれは人間存在が、なぜ「〈生存〉の実現」のみならず「〈現実存在〉の実現」や「〈継承〉の実現」をも必要とする存在となったのか、という問題についても答えられるようになるだろう。
つまりわれわれは生物進化の過程において、すでに「〈生〉の舞台装置」としての〈社会〉がなければ〈生存〉を達成できない身体となっている。そしてだからこそ、われわれには「〈生〉の舞台装置」を皆で支えていくための「〈現実存在〉の実現」が求められ、それを次世代に受け渡していくための「〈継承〉の実現」が求められるといったようにである。
【第六章】「〈生〉を変容させる〈社会的装置〉とは何か」では、以上の「人間的〈生〉」をめぐる議論を踏まえることによって、【第二部】において「〈社会〉と〈人間〉の切断」と呼んできた第三の特異点の内実について、再描写することを試みる。
最初に焦点をあてるのは、これまで〈社会的装置〉と呼んできたものに対するより詳しい分析である。とりわけここでは、〈自己完結社会〉の成立において決定的な役割を果たしてきた〈社会的装置〉が、人間存在にとって根源的な「〈生〉の舞台装置」としての〈社会〉に対して、いかなる点で異なっているのかということである。
例えば「〈生〉の舞台装置」が発揮する〈根源的葛藤〉の緩和機能と、〈社会的装置〉の発揮する人々の行為の調整機能との間には、明らかな連続性がある。しかし前者が“意味”によって支えられているのに対して、後者は根源的には“意味”を必要としていない。
ここから本書では、〈社会的装置〉の本質が、「〈生〉の舞台装置」としての〈社会〉を構成する“三つの成分”のうち、「意味体系=世界像」のみが縮小し、「社会的構造物」と「社会的制度」のみが異常なまでに突出している点にある、ということについて見ていこう。
本章の後半では、このことを念頭に、第二の特異点から第三の特異点への移行の過程についても詳しい考察を行っていく。われわれはここで、〈生活世界〉の人間的基盤とも言うべき“地域社会”の解体こそが、この移行に決定的な意味をもたらしたことについて指摘しよう。
確かに〈社会的装置〉の主要部分は、第二の特異点である「近代的社会様式の成立」に伴って出現してきたと言うことができる。しかしおそらく〈生活世界〉が強固な人間的基盤を有しているうちは、「意味体系=世界像」は〈生活世界〉に担保されており、「社会的構造物」と「社会的制度」の複合体である〈社会的装置〉は、依然として“補助装置”という形で〈生活世界〉に埋め込まれていた。
つまり地域社会の消滅によって〈社会的装置〉が〈生活世界〉から自立化し、人々が〈社会的装置〉に全面的に依存する「〈ユーザー〉としての生」が完成したとき、はじめてわれわれは第三の特異点に到達したと言えるのである。
「人間的〈生〉」をめぐる一連の分析によって、われわれは当初の問題に対しても、異なる視点を得ることができるようになるだろう。
まず〈関係性の病理〉に関することで言えば、今日のわれわれは〈社会的装置〉の文脈に立つ限り――とりわけ「経済活動の倫理」に見られるように――財やサービスを媒介として、人格的要素をほとんど排除したまま、他者と容易に結合することができる。しかしそれとは対照的に、〈社会的装置〉の文脈を少しでも外れてしまうと、われわれは関係性を築いていくために、今度は“私”という人格的存在を「むき出し」にしなければならない。
本章では、こうした歪で極端な関係性の背後に、“意味”を不要とする〈社会的装置〉へのわれわれの全面的な依存と、それによってわれわれが自らの内に潜む〈根源的葛藤〉を適切な形で緩和することができなくなっている事態が関わっているのではないかということを指摘しよう。
また〈生の混乱〉に関することで言えば、われわれは「〈生〉の不可視化」や「〈生活世界〉の空洞化」といった概念を通じて、それが「〈ユーザー〉としての生」というあり方そのものに含まれる問題であるということを再確認できるようになると思われる。
本章ではここで、われわれが〈自己完結社会〉の成立に至って、はじめて自らがこの世界で「生きる」ことの意味を、時空間的な〈存在の連なり〉の文脈から理解することができなくなったということについて考える。
そして〈存在の連なり〉のなかに自らを根づかせることができない人間は、どれだけ私的な願望としての「自己実現」を達成しようとも、他者と関わり、意のままにならない〈生〉の現実に対峙していけるだけの現実感覚を持ちえないこと、意のままにならない世界のなかで、おのれの存在に確信を持ち、それを肯定していけるだけの〈存在の強度〉を保持することはできないということについて指摘したい。
以上の【第三部】の議論において特に注目すべきは、本書が「人間的〈生〉」の本質を論じる際に、徹底して「〈生存〉の実現」という契機を重視している点である。このことは、これまで人文科学的な知を支えてきた世界観、人間観において、人間の本質を問題にするうえで、この契機が十分に意識されてこなかったことを踏まえてのことである。
われわれは【第五章】において、それを「暮らしとしての生活」に対置される「精神としての生活」と呼ぶことになるが、そこには人間の〈生〉の本質が〈生存〉から切り離れたところ、〈生存〉を超えたところにこそあるという信念が潜在しているように思える。
しかし人間的な〈生〉の根底には、歴然として〈生存〉の問題が横たわっているのであり、本書では、この問題を考慮しないいかなる人間学も、人間の〈生〉の本質を掌握することはできないと考えるのである。