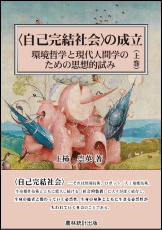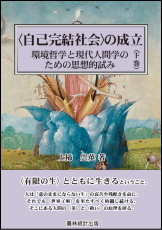『〈自己完結社会〉の成立』
【序論】――本書の構成と主要概念について
(2)「現代人間学」の方法論的特徴と〈思想〉の実践
本書が依拠する「現代人間学」は、そうした問題意識に基づく、ひとつの新しい哲学的方法論であると言える。ここではその特徴について、以下の四つの原則、すなわち①「何よりも優先されるべき〈思想〉の創造」、②「絶対的普遍主義の否定」、③「世界観=人間観の提示」、④「強度を備えた〈思想〉の希求」という観点から、具体的に見ていくことにしよう。
まず、第一の原則である「何よりも優先されるべき〈思想〉の創造」は、これまで見てきた危機感が反映されたものである。つまり「現代人間学」においては、哲学的な問題を扱う際に、不透明な時代の現実を受けて、思想の創造それ自体が重視される。しかもそこでは、ときに文献学的な意味での精密さや体系性よりも、徹底して新たな着想、新たな概念、そして新たな理論の構築が優先されるということである
(7)。
ただしこの第一原則には、より深い含意が込められている。そしてそのことを理解するためには、われわれはいったん、そもそも“思想”とは何かという問題について考えてみる必要があるだろう (8)。つまり、人間はなぜ思想を生みだすのか、なぜ人間の世界には思想というものが存在しなければならないのかという問題に他ならない。
出発点となるのは、そもそも人間は、根源的に世界を了解し、他者を了解するための意味と言葉を必要としている、という存在論的な前提である。例えば人間存在にとって、世界は常に不可解なものであって、決して意のままになるということはない。そこでわれわれが出会う他者もまた、常に計り知れない存在、意のままにならない存在として現前する。それでも人間は、そうした世界において、そうした他者と生きることを宿命づけられているのである。
つまり世界や他者との対峙を避けられない人間が、その与えられた宿命と向き合うこと――本書ではこのことを後に〈世界了解〉と呼ぶことになる――そしてそうして紡ぎだされた意味や言葉こそが、思想の起源だと言えるのではないかということなのである。
そのように考えれば、思想の創造が求められる現代とは、人々が改めて世界や他者との了解を必要としている時代であるということを意味するだろう。思想の創造とは、直接的には、その新たな了解のための意味と言葉を実際に創出していくことを意味するのである。
ただし、それだけではない。人間存在は遠い古の時代から、その時々の要請にしたがって思想というものを紡いできた。いまのわれわれを取り巻いている無数の意味と言葉は、まさしくそうした人々によって紡がれ、しかもそれが幾世代ものときを越えて受け継がれてきたものなのである。そのことを思えば、思想の創造が、単に文字通りに意味と言葉を紡ぐことのみを意味しないということが分かるだろう。
それは例えば、古の時代において、それを必死に紡いできただろう無数の人々、あるいはわれわれが決して知りえぬ未来において、いつしかそれを紡いでいくことになるだろう無数の人々に思いを馳せること――本書ではそうした意識が依拠するものを〈存在の連なり〉と呼ぶことになる――そしてそこから、われわれ自身が自らの生きる時代の現実と対峙し、新たな意味と言葉をめぐって格闘していくということを意味しているからである (9)。
こうして紡ぎだされるもののことを、本書では改めて〈思想〉と呼ぶ。「現代人間学」において「〈思想〉の創造」と言うとき、念頭に置かれているのはこうした含意なのである。
次に第二の原則となる「絶対的普遍主義の否定」であるが、それはこうした「〈思想〉の創造」を試みる際、「現代人間学」においては、それを決して唯一絶対的な意味での「普遍的な真理」として希求することはない、ということを意味している (10)。
前述のように「〈思想〉の創造」は、〈存在の連なり〉に思いを馳せ、時代の現実と対峙し、格闘していくことを通じて実践される。それは直接的には「われわれはいかなる時代を生きているのか」、「この時代に人間をどのように理解すべきなのか」という二つの問いに答えていくことでもあるだろう。
ただしそうして紡ぎだされた〈思想〉は、決して唯一絶対という意味での真理になることはない。なぜなら〈思想〉は、例外なく、それを紡ぐものが生きる時代の枠組みによって規定されたものとなるからである。同じ時代を生きるもの同士であっても、見えている現実が同じであるとは限らない。そのため創造された無数の〈思想〉は、必ず相互に矛盾をはらむことになり、それらがひとつの体系に統合されるということも決してないと言えるからである。
一部の人々は、「それでは意味がない」と言うかもしれない。なぜなら伝統的な西洋哲学においては、「普遍的な真理」を解明することこそが、その至上の目的であるとされてきた側面があるからである
(11)。
その背後にあるのは、この世界には唯一絶対的な真理、理念、価値、正義といったものが存在する――現時点の人類がその具体的な認識に到達しているかどうかは別として――という形而上学的な前提である
(12)。
しかし「現代人間学」は、そうした前提には依拠しない。むしろいかなる〈思想〉も“不完全”であるということを覚悟しつつ、それでも時代の求める“より良きもの”として、人々が〈思想〉を紡ぎ続けていくことを肯定するからである。無数の〈思想〉の試みが、誕生しては消えて行く。「現代人間学」は、そうした〈思想〉のあり方そのものを信頼しているのである
(13)。
それゆえ〈思想〉を創造するものに求められるのは、流行りの言説を習得することでもなければ、超越的な観点のもとで人々を見下ろすことでもない。あるいは「正しさ」をめぐって知的乱闘を繰り返すことでも、「完璧さ」を求めて理論武装に邁進することでもない。そうではなくて、まずは時代に規定されたおのれ自身を問題とすること、そして自らの確信を〈思想〉へと昇華させるべく、座してあらゆる苦しみに耐え抜いていくことであると主張する (14)――それを“決断主義”と呼ぶのであれば、〈思想〉の実践とは、まさしくそうした決断を要する実践であるとも言えるだろう (15)――。そして世代を越えて互いを触発し、知恵を出し合うことによって、総体的営為としての「〈思想〉の創造」を支えていくことであると主張するのである。
しかし「普遍的な真理」の探求を否定すると言うのであれば、「現代人間学」は、いったい何を目指すことになるのだろうか。
例えば前述したように、その試みは確かにひとりひとりに現実との対峙を要請している。とはいえそれは、例えば“現場”へと直接足を運んだり、政策的次元において何か“役に立つもの”を提言したりするといったことではない。「現代人間学」が挑むべき舞台は、あくまで〈思想〉の次元にあるからである。そしてこのことに関わるのが、第三の原則である「世界観=人間観の提示」である。
われわれは先に、〈思想〉の起源には世界や他者への了解があると述べた。注目したいのは、このことが“哲学”にもたらす新たな意味づけについてである。
というのも了解を希求する人間の原点に立ち返れば、そもそも哲学も宗教も、あるいは芸術さえも、いずれも何らかの〈思想〉を表現したものであるとは言えないだろうか。そして芸術が、必ずしも言語を用いない〈思想〉の表現であるとするなら、〈哲学〉とは、逆に徹底的に言語を駆使したもの、とりわけ言語的に構造化された理論を駆使して〈思想〉を表現したものであると言えるからである (16)。
したがって〈哲学〉には、「普遍的な真理」の探究とは別のところで、やはり固有の役割があると言わなければならない。
筆者は先に、哲学には事物の理解に先立つ基礎概念の整備という役割があると述べたが、より厳密に言えば、基礎概念が有効なものとなるためには、諸概念の背景において、豊かな世界観や人間観が広がっていなければならない(17)。つまり〈思想〉の表現たる〈哲学〉に求められる真の役割とは、基礎概念の整備を通じて、こうした“世界観”や“人間観”そのものを新たな形で提示していくことにあると言えるのである。
実際われわれが経験している今日の知の動揺は、単なる基礎概念の問題にとどまらず、その背景にあるべき世界観や人間観そのものの限界の表れである可能性がある。そうした意味においても、われわれはいまこそ〈哲学〉を必要としていると言えるだろう。「現代人間学」が目指しているのは、そうした現実を受けての〈哲学〉の実践なのである。
とはいえ、われわれが優れた〈思想〉の実践を結実させるためには、例えば理論としての巧妙さ、論理的な説得力を追求するだけでは不十分である。そしてこのことを問題とするのが、第四の原則となる「強度を備えた〈思想〉の希求」である。
まず、ここで「強度」と言うとき、そこには〈思想〉が持つ二種類の潜在力のことが念頭に置かれている。
そのひとつは、時代の不確実性や不透明性を前にしても、なおその〈思想〉が耐えうる潜在力のことを指し、もうひとつは、その〈思想〉に備わっている人心を動かしうるだけの言葉の潜在力のことを指している。つまり創造された〈思想〉であっても、それが時勢によって陳腐化することなく、ときを経てもなお色褪せない何かを残しうるものなのか、そしてすべてが理解しがたくとも、人々の内面に働きかけ、そこに確かな痕跡を残しうるものなのか、ということである。
われわれが「強度を備えた〈思想〉」に至るためには、まずはその〈思想〉が、どれだけ時代を超えた人間存在の本質を掌握しているのか、そしてその言葉が、どれだけ現代における“救い”、すなわちわれわれの必要としている世界や他者に対する了解にまで触れえるものになっているのかが問われるだろう。
さらに言えば、それをどれだけ“美意識”として表現することができているのか、このことも重要である。優れた〈思想〉には、優れた理論や表現だけでなく、例外なく優れた美意識が伴っている。われわれ人間には、自らの行いがはたして「美しい」ものだったのかと問い続ける力がある。「現代人間学」が目指しているのは、こうした人間存在の側面をも踏まえたうえでの、新たな〈思想〉の実践だと言えるのである。
(3)本書における三つのアプローチ へ進む
(7)もちろん「現代人間学」においても、既存の議論に対する位置づけを示すためには、一定の文献学的な注釈は必要となる。しかしこのことを強調したのは、われわれがこれまで文献学的な問題を優先するあまり、常々この「〈思想〉の創造」を蔑ろにしてきた過去があったからである。われわれが偉大だと見なす思想家の書物にあっても、そのすべてが文献学的な精密さや体系性を備えているとは限らない。文献学的な誤りを含んでいるもの、体系化されることなく筆が置かれているものも数多く存在する。それでもなお、それらが後世に残されてきたのは、そこに新たな世界観を切り開き、人々の内面に訴えかける〈思想〉としての潜在力があったからではないか。「〈思想〉の創造」と文献学的な精巧さは、ときに両立できないこともある。その意味においては、「〈思想〉の創造」を実験的に行う人々と、そうした試みを整理し、既存の知的遺産のなかにつなぎとめていく人々が相互に連携していく必要があるとも言えるだろう。しかしいずれにしても、わが国の知識社会において決定的に不足しているのは、やはり「〈思想〉の創造」を試みていく人々であると思われる。
(8)代表的な辞書によれば、“思想”とは、第一に「心に思い浮かべること。思いをめぐらすこと。また、その考え」を指し、第二に哲学的な含意として「思考されている内容。広義には意識内容の総称。狭義には、直接的な知覚や具体的な行動と対比して、文や推論などの論理的な構造において理解されている意味内容」、第三に「社会、人生などに対する一定の見解」のことを指すとされている(『日本国語大辞典』 2007)。
(9)増田敬祐は、こうした〈存在の連なり〉のもとで〈思想〉の実践を試みることを「名付けられたものを名付け返す」と表現した。この言葉は【付録一】の「『現代人間学・人間存在論研究』発刊によせて」のなかにも収められている。またその真意については、文芸誌『夜半』に掲載の朝市羽客(2015)の論考も参照のこと。
(10)この第二原則については、ある種の矛盾を感じる人々もいるかもしれない。なぜなら「人間存在の本質」を問うということは、時代を超えた人間の特性を掌握するということを意味しており、それはある種の普遍性を問題としているとも言えるからである。とはいえそれが、唯一絶対的なものとして提起されないという点にこそ、ここでの規定の本質がある。〈思想〉を言語理論によって表現するためには、ある種の「普遍化」は避けられない。第二原則が念頭に置いているのは、先の「絶対的普遍主義」と、こうした〈思想〉の形成に伴う「普遍化」とを厳密に区別するということなのである。この問題については、【注13】も参照のこと。
(11)もちろん伝統的な哲学の議論においても、多元主義という形で真理の複数性を主張しているものがある。しかしそこで焦点となるのは、例えば「真理の一元論と多元論のうちどちらが真理であるのか」といった論争、あるいは方法論上の問題として真理の特定が困難であるために、やむを得ず多元主義を採用するといった性格のものである。これらの思考の根底には、依然として「絶対的普遍主義」が横たわっていると言えるのである。
(12)【第九章】でも触れるように、西洋世界が依拠しているこの形而上学的前提は、われわれが想像する以上に根深い歴史的、文化的文脈を伴っている。それは遡れば、おそらく人間を称揚したルネッサンス期のキリスト教にまで行き着くだろう。
(13)例えば相互に矛盾をはらんだ「言説イ」、「言説ロ」が存在するとき、「絶対的普遍主義」の立場から言えば、そのいずれかが間違っているか、あるいはその両方ともが間違っていて、未だ発見されていない「言説ハ」こそが「普遍的な真理」であるということになる。これに対して「現代人間学」においては、そもそも「普遍的な真理」としての「言説ハ」の存在を認めない。その代わりに「言説イ」と「言説ロ」のいずれもが、人間存在の“ある種の本質”を捉えている可能性があるということを重視する。つまりそこでは、たとえ矛盾する言説であっても緊張関係を保ちつつ共存できるのであり、これは「絶対的普遍主義」の立場からは決して導出されない帰結であるだろう。現時点でどれほど「正しい」とされている言説も、異なる時代においては「誤り」とされる可能性がある(当然、その逆もある)。またいかなる〈思想〉であっても、それが誕生したことには“理由”がある。ある時代に、ある属性の、ある立場に立つ人間が、ある動機のもとで「何ものかが重要である」と切実に思案した。それだけのことであっても、そこには時代の要請するある種の“必然性”がある。それは「絶対的普遍主義(普遍的な真理)」とは異なる、限定された意味合いにおける、ある種の「普遍性」である。と同時に、そうした時代の“必然性”は、常々一見他愛のない人々の生活の細部において表現される。そのような意味において、個人的なことは「普遍的」なことであり、「普遍的」なことは個人的なことである、とも言えるだろう(【補論二:注62】も参照)。特定の〈思想〉を「肯定する」ということは、そうして紡ぎだされる何ものかを「正しい」と見なすことではなく、それが存在する“理由”を理解するということなのである。本書で言う「強度を備えた〈思想〉」についても、それをはかる絶対的な基準は存在しない。例えばある人々が「言説イ」を見て称賛しても、別の人々はそれを見て批難することになるかもしれない。だが、それでいいのである。来たるべき何ものかが、これからもより良き〈思想〉を紡ぎあげ、変わりゆく時代の要請にきっと応えてくれるだろう。「現代人間学」は、そうした信頼に立脚しているからである。
(14)もちろん、ここでの主張は万人に対してのものではなく、あくまで「〈思想〉の創造」に従事すべき人々に対して向けたものである。「〈思想〉の創造」は誰にでもできるものではない。しかしそうした能力がありながら手をこまねいている人々がいるのだとすれば、そうした人々にこそ、筆者はこの言葉を投げかけているのである。なお、こうした実践の側面のことを、筆者は吉田健彦の言葉を借りながら「とどまる思想」と呼んできた。この言葉は【付録一】の「『現代人間学・人間存在論研究』発刊によせて」のなかにも収められている。
(15)筆者がここで敢えてこのように表現したのは、國分功一郎(2015)や千葉雅也(2017)といった近年の識者が、決断主義をあまりに否定的なものとして位置づけているからである(なお、他にも決断主義を論じたものとして宇野常寛(2011a)があるが、彼の場合はやや異なる位置づけが必要であると思われる。というのも宇野にとって、決断主義は「ポストモダン」的状況への必然的な応答として、一度は通過しなければならないものとして位置づけられており、焦点となっているのは、そうした決断主義的状況を所与として、なお人々がいかにしてより良き生を実現できるのかという部分であるように思えるからである)。彼らにとって決断主義とは、自らが拠るべき確かな準拠点が不在であるとき、暫定的にせよ、“決断”によって特定の命題や枠組みを自らの準拠点とすることを指している。そして両者は、そうした態度が何ものかに対する盲目的な絶対視であるがゆえに危険であると主張する。しかしそうした事態があるとすれば、それは決断主義が現実との格闘を拒絶し、現実否定の理想主義に没入したときであるだろう。むしろ何ものかに対する“決断”がなければ、〈思想〉を創造していくことなど不可能である。そもそも有限な存在としての人間は、いつの時代も何かを“決断”することに迫られてきた。さまざまな選択すべき局面において、真に絶対的なことなど、人類は一度たりとも知りえたことはなかったからである。“決断”なしに人間が生きることなどありえない。重要なことは“決断”そのものの善し悪しではなく、いかに“決断”するのかということだろう。
(16)言語を駆使する〈思想〉の形態として、他にも“詩”や“文学”という表現方法がある。〈哲学〉が、言語の持つ理論や論理性の力を生かした表現方法であるとすれば、詩や文学は、言葉それ自体の、あるいは物語の持つ響きの潜在力を生かした表現方法であると言えるかもしれない。
(17)実際、“理性”や“自由”を含む先の基礎概念がその有効性を保持することができたのは、その背後に西洋近代哲学という、強力な「世界観=人間観」が担保されていたからである。