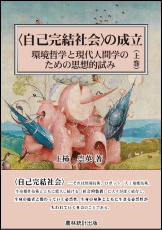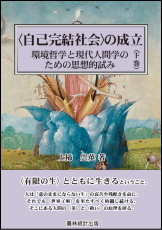『〈自己完結社会〉の成立』
【序論】――本書の構成と主要概念について
(4)本書の構成について 第2部
【第二部】「「人間的〈環境〉」の分析と人類史における連続性/非連続性」からは、こうした問題意識を受けて、人間存在の本質を説明するための理論的枠組みを実際に構築することを試みていく。【第二部】において焦点となるのは、前述した第一のアプローチ、すなわち「環境哲学」を用いた人間の解明についてである。
【第三章】「人間存在と〈環境〉」では、われわれはまず、「環境哲学」の基本的な枠組みを整備するために、そもそも“環境”とは何か、とりわけ自然科学的な文脈での客観的な環境とは異なる、存在論的な〈環境〉の概念について考える。
ここで手がかりとなるのは、“生物存在”にとっての環境とは、主体によって定義される相対的なものであるということ、また特定の生物存在が自らの存在を十全に成立させるためには、そこに固有の環境が不可欠であるという認識である。
本章ではこうした存在論的な〈環境〉の概念を念頭に、人間存在にとっての固有の〈環境〉、すなわち「人間的〈環境〉」の構造について詳しく分析していく。
人間存在が一般的な生物存在と異なるのは、「自然生態系」の表層に「人為的生態系」としての〈社会〉を創出し、その二重の〈環境〉のなかで生を営むという存在様式においてである。ここではその「人為的生態系」が、“物質的基盤”となる道具や耕地、建築物といった「社会的構造物」に加えて、“非物質的基盤”となる、人々を組織化する「社会的制度」、および概念や価値、世界観といったものを含んだ「意味体系=世界像」という“三つの成分”によって構成さていることについて詳しく見ていこう。
この「人為的生態系」としての〈社会〉は、生物個体としての人間にとってきわめて重要な意味を持っている。なぜならそれは、人間によって創出されると同時に、人間自身を成立させ、人間自身を規定するものとして現前するからである。
つまり生物学的に「ヒト」として生まれたわれわれは、こうした「人為的生態系」の影響を受けることによってはじめて「人間」となる。またわれわれがいかなる人間として成長するのかということは、影響を受ける「人為的生態系」のあり方によって異なるものとなるからである。
加えてこの「人為的生態系」としての〈社会〉は、繰り返し次世代へと受け継がれ、その過程において蓄積されるという特徴を持っている。つまり人間は、前世代から〈社会〉を受け継ぎ、生存の過程においてそれを改変させるものの、次世代にとっては、それが自らを規定する“所与の〈環境〉”として現前する。そして一連の営為が繰り返されることによって、「人為的生態系」としての〈社会〉は、世代を超えて絶え間なく膨張していくことになるのである。
【第四章】「人類史的観点における「人間的〈環境〉」の構造転換」では、この「人間的〈環境〉」の概念を前提に、700万年の人類史について改めて考えていきたい。
焦点となるのは、人類史には存在様式の“質的転換”とも呼べるいくつかの“特異点”が存在するということ、そしてそれが人間存在のあり方に対していかなる意味をもたらしてきたのかということである。
第一の特異点は、約1万年前の「農耕の成立」である。
人間は自らの生存のために食料を必要としているが、「農耕の成立」とは、そのための社会的基盤が人為的な食物網を自ら創出/管理していく形式へと移行することを意味している。この特異点以降、人間によって「自然生態系」の表層に創出される「人為的生態系」は、「社会的構造物」という意味でも、「社会的制度」や「意味体系=世界像」という意味でも、爆発的に肥大化するようになっていく。
本章ではそれを、人間と自然の直接的な関係性が縮小し、両者の間を常に「人為的生態系」としての〈社会〉が媒介するようになるという意味において、「〈人間〉と〈自然〉の間接化」と呼ぶことにしよう。
次に第二の特異点は、「近代的社会様式の成立」である。それは直接的には数100年前の西欧において、「国民国家」、「市場経済」、「化石燃料」を基調とした新しい社会様式が出現することを意味している。
この特異点以降、「自然生態系」は科学技術を用いた予測とコントロールの制御下に置かれるようになり、「人為的生態系」としての〈社会〉は、化石燃料を動力としつつ、それ以前の時代とは比較にならないほど爆発的に肥大化していくことになる。「人為的生態系」としての〈社会〉は、ここで「自然生態系」からの直接的な“制限”から外れ、また「自然生態系」との“整合性”を欠いたまま、まさに無限に膨張していくように見えるものとなる。
本章ではこのことから、この第二の特異点のことを「〈社会〉と〈自然〉の切断」と呼ぶことにしよう。
問題となるのは、われわれが今日直面している〈自己完結社会〉の成立が、こうした人類史的射程において、いかなる位置を占めるのかということである。われわれはここで、〈自己完結社会〉というものが、700万年あまりの人類史の文脈のもと、いかなる点において連続しており、また連続していないのかという問題について考えていこう。
おそらく〈自己完結社会〉は、「人為的生態系」というものを創出し、それを絶え間なく次世代へと継承していくわれわれの本性、そしてその過程で自らの存在様式を繰り返し変容させてきたわれわれの歴史の延長線上にある。しかしそこには、やはり過去との“非連続性”と呼べるものもまた存在するはずである。
本章ではそれを第三の特異点、すなわち歯止めを失った「人為的生態系」としての〈社会〉が、今度は人間それ自体との“整合性”までをも失いつつある事態であると理解し、それを改めて「〈社会〉と〈人間〉の切断」と呼ぶことにしたい。
以上の【第二部】の議論において注目すべきは、生物存在としての人間という観点である。
これまで人文科学的な知を支えてきた世界観、人間観においては、人間を定義する際、他の生物存在との違いの部分を過剰に意識する傾向があった。そこにあったのは、あらゆる生物存在が本能によって規定されるのに対して、人間のみが理性と自由とを持つがゆえに、生物学的本性から解放されうるといった人間観である。
それゆえ人間を生物存在との連続性のもとで語ることは、そこではしばしば危険であるとさえ考えられてきた(19)。しかし人間が生物存在の一種であることは疑いえない。むしろ本書では、われわれがそうした連続性と向き合うことによってこそ、新たな人間の〈思想〉を構想していく手がかりが得られると考えられているのである。
(4)本書の構成について 第3部 へ進む
(19)例えば社会生物学論争の根底にあったのは、進化論や生物学の知見が、自由、理性、人権といった、西洋近代が築きあげてきた核心的価値理念を破壊するかもしれないという恐れであった。詳しくはセーゲルストローレ(2005)を参照。