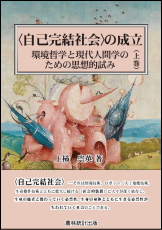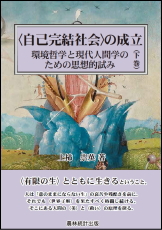用語解説
「存在論的自由」 【そんざいろんてきじゆう】
- 「問題は、こうした人間に対する規定が、やがて「政治的自由」の脈絡から外れ、次第に人間存在そのものへと一般化された「存在論的自由」を論じるものへと拡張されていったことである。そしておそらくそのときにこそ、われわれは〈無限の生〉へと続く扉を開くことになったのである。」 (下巻 112-113)
「自由の人間学」から派生した理念で、人間存在は自らの存在を規定するあらゆる外力(「存在論的抑圧」)から解放され、自らの存在のあり方を自己決定していくことこそがあるべき姿(「本来の人間」)であると考える立場。
「自由の人間学」にはもともと、「時空間的自立性」(人間の存在論的な実体が、環境や他の生物、他者といった外的なものに先立ち、また独立した形で存在しうるという想定)という形で人間の存在論的独立性を論じる視点が含まれていたが、それはもともと「政治的自由」を念頭に置いたものであり、「存在論的自由」は、そこで想定されていた前提が、次第に人間の存在のあり方にまで拡張されていく形で成立していった。
I・カント(I. Kant)の「意志の自律」(Autonomie)は、その過渡期を象徴するものであり、「存在論的自由」の理念がその潜在力を開花させるのは、マルクス主義を頂点とした、自由の実現へと向かう“人類の物語”が終焉してからである。
「大きな物語」の失墜後、その理想は“人類の物語”としてではなく、“個人の物語”(諸個人が自らを規定する外力から解放され、自らの存在のあり方を自己決定していく物語、「かけがえのないこの私」)という形で展開していった。
そして「〈ユーザー〉としての生」が拡大し、人間的現実として、住むべき場所、携わるべき仕事、関わるべき他者など、個人的な〈生〉を形作るあらゆる事柄が自発性と自由選択に基づいてしかるべきだとの認識される時代になると、その理想は、自意識によって創出された「こうでなければならない私」の理念を「現実のこの私」に具現化させることを意味するようになっていく。
しかしながら「存在論的自由」の理念は、根源的な部分で人間の現実に反しているため(自らに先立つものを通じて〈自己存在〉を形成し、「意のままにならない他者」や「意のままにならない身体」との〈関係性〉や〈共同〉を通じて生きて行かなければならない人間の現実、あるいは〈有限の生〉の五つの原則を受け入れることができなくなるため)、「現実を否定する理想」となって、理想を追えば追うほどに、絶え間なく現実を否定し続けなければならない「無間地獄」に陥ることになる。
この問題は、〈無限の生〉の「世界観=人間観」がなぜ「敗北」するのかということを理解するうえで重要な鍵となり、また〈自立的な個人〉の思想を含む「自由の人間学」から派生した人間の理念のどこに問題があるのか、さらには権力論を含む「ポストモンダン論」から派生したアプローチがなぜ限界を含んでいるのかを説明するうえでも重要な視点となる。