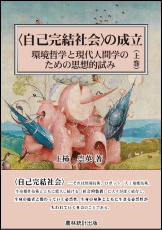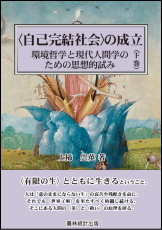『〈自己完結社会〉の成立』
【序論】――本書の構成と主要概念について
(4)本書の構成について 第1部
さて、ここからは本書の構成にしたがって各章の内容について概観し、そのなかで本書を構成する主要概念について触れておくことにしたい。この作業が、本書を理解するための第三の補助線となるだろう。
まず、【第一部】「時代と人間への問い――〈自己完結社会〉への目なざし」では、【はじめに】において素描した〈自己完結社会〉の成立をめぐる本書の基本的な問題意識について、「われわれはいかなる時代を生きているのか」という問いのもとから述べていくことになる。
【第一章】「「理念なき時代」における“時代性”」では、「理念なき時代」という視点から、現代社会が置かれた状況について分析していこう。
本書で「理念なき時代」と言う場合、そこには三つの意味が込められている。それは第一に、人間社会の理想をめぐって明確な理念と対抗軸を伴っていた「20世紀」とは対照的に、現代社会はあらゆる対抗軸を喪失した文字通り不透明な時代であるということ、第二に、「20世紀」の枠組みがすでに持続不可能であると認識していながら、われわれは依然としてそうした枠組みを延長することによってしか未来を語れずにいるということ、そして第三に、そうした事態が、われわれの人間そのものを理解し説明するための枠組みにまで及んでいるということである。
本章で注目するのは、情報技術、ロボット/人工知能技術、生命操作技術という三つの技術領域である。そしてそうした現代科学技術が、「理念なき時代」の傍らで、われわれの存在様式にいかなる変容をもたらしているのかについて考えていく。
その変容とは、われわれの生活世界を包含する高度な自己調整能力を備えた巨大な〈社会的装置〉の建設、そして人間存在の、そうした〈社会的装置〉に対する圧倒的なまでの依存、すなわち〈自己完結社会〉の成立という事態である。
われわれはここで、【はじめに】でも述べた〈生の自己完結化〉、〈生の脱身体化〉、〈関係性の病理〉、〈生の混乱〉といった、〈自己完結社会〉を説明するための中核概念について再び取りあげることになるだろう。
〈社会的装置〉への依存は、われわれが生身の他者と関わることの必然性を喪失させ、同時にわれわれが身体というものに拘束される必然性を喪失させていく。そして現実社会においては、そうした事態がもたらす矛盾が、すでに対人関係における多大な困難や、生の実感や生きる意味に対する混乱として現れているということである。
本章では、こうした〈自己完結社会〉に生きる人間のことを〈ユーザー〉と呼ぶことにしよう。それは〈社会的装置〉に全面的に依存し、〈社会的装置〉がなければ生きていくことができなくなった現代人の姿を比喩的に表現したものである。
そして本章では、締めくくりとして二つの“人間の未来”について予備的な考察を行っておきたい。そのひとつは、〈自己完結社会〉がいつしか限界に達して崩壊してしまう未来の姿、そしてもうひとつは、逆に〈自己完結社会〉が崩壊することなく、極限にまで進行した未来の姿についてである。
【第二章】「人間学の“亡霊”と〈自立した個人〉のイデオロギー」では、これまでわれわれの社会が依拠してきた人間の理想とは何か、そしてその理想に含まれる問題点について見ていく。
それは【はじめに】でも触れた〈自立した個人〉の思想、すなわち人間の本質を個人に見いだし、それぞれの個人が何ものにもとらわれることなく、十全な自己判断/自己決定を通じて、意志の自律を達成することを理想とする、ひとつの人間学のことである。
〈自立した個人〉の思想は、戦後の日本社会においてきわめて重要な位置を占めてきた。しかしその思想は、すでに〈自己完結社会〉の成立という新たな事態に対して有効な説明能力を失ってしまっている。
本章ではこのことを説明するために、二つの点に着目しよう。ひとつは、そこで想定されている“シナリオ”についての問題である。例えば〈自立した個人〉の思想においては、「自立」を阻むのはあくまで外的な抑圧や強制力であると考えられている。そのためそこでは、「解放」さえ実現すれば、人々は自ずと「自立」するということになる。
しかし現実には「解放」が進展しても、人々は必ずしもそうした理想的人間類型になることはない。それでも〈自立した個人〉の思想は、そうした現状を、あくまで「解放」の不徹底という形でしか認識することができない。その結果として、際限のない“自由”と“平等”の拡大、絶え間のない「解放」を求める「無限の循環構造」に陥ってしまうのである。
ただし、より重要なのはもうひとつの点、【はじめに】においても触れたように、この「自立」のための「無限の循環構造」が、実際には〈生の自己完結化〉および〈生の脱身体化〉と表裏の関係にあるという問題である。
このことを説明するために、本章では〈ユーザー〉としての「自由」と「平等」という概念を導入しよう。それは、われわれの実現してきた“自由”と“平等”が、現実には〈社会的装置〉への依存によってはじめて実現されるものであるということを意味している。
つまり「自立」のための「解放」は、確かに「自由」と「平等」を拡大させると言えるものの、それは同時に〈社会的装置〉への依存を通じて、“他者”や“身体”そのものからの「解放」という問題と地続きの関係にあるのである。このことは、問題解決のための「解放」の拡大が、結果的にわれわれをより深刻な〈関係性の病理〉と〈生の混乱〉に直面させるという逆説を意味しているのである。
以上を通じて【第一部】では、われわれがいま一度、人間存在の本質とは何かという根源的な問いにまで遡らなければならないということ、そして既存の言説に依存することなく、人間存在を新たな形で説明可能な理論的枠組みそのものを構想し、人間存在が“生きる”ことの意味をいま一度問題としなければならないということが提起されるのである。