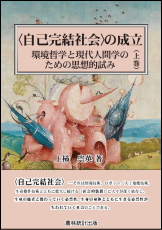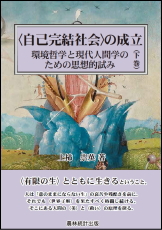『〈自己完結社会〉の成立』(上巻)
【序文】――はじめに(その2)
さて、以上の説明を通じて、読者には本書が扱う問題についてひとつのイメージを持ってもらうことができたのではないだろうか。とはいえここでは、本書の性格について、もう少し説明しておかなければならないことがある。
例えば大きな括りから言えば、おそらく本書は「哲学」の書物に分類されると思われる。
とはいえ本書は、執筆のスタイルから言っても、展開される内容から言っても、一般的な哲学関連本とは相当に異なるものとなっている。具体的に言えば、本書は一般的な哲学関連本にあるような、著名な西洋哲学の理論を取りあげて、それを手がかりに何かを説明するという方法は採用しない。
そうではなく、本書では目的を達成するために、必要となる基礎概念をひとつひとつ自ら整備し、理論的枠組みそのものを独自の形で構築する。
そのため例えば、理性、自由、平等、権利、連帯、正義、権力、抑圧、資本主義、全体主義といった、これまで戦後の人文科学を支えてきた基礎概念の多くは、ここでは議論の中核には位置づかない(その代わりに本書では、〈環境〉、〈生〉、〈関係性〉、〈生存〉、〈継承〉、〈間柄〉、〈共同〉、〈役割〉、〈信頼〉、〈許し〉、〈悪〉、〈救い〉、〈美〉といった独自の概念を駆使することになる)。
さらに言えば、本書は過去の言説の整理や検討から出発して自説の展開へと向かうという手法も採用しない。
そうではなく、最初から自説の展開を主軸とし、関連する諸説は随所で必要に応じて言及するという形で書かれている。もちろん諸説との相違点は、自説の新しさを正確に伝えるためには必要となることである。だが本書では、そうした作業は最低限に抑え、あくまで新しい理論の構築を優先させているのである。
本書がこうしたスタイルを採用する理由のひとつには、いわゆる正統派の哲学研究への反省がある。つまりこれまでの多くの哲学研究が、過去に蓄積された膨大な文献や、学説的体系性に基づく「正確さ」、「普遍性」に固執するあまり、意味を与えるべき同時代の人間的現実と向き合う力を喪失してきたように見えるからである。
しかしここにはもうひとつ、本書の主題である〈自己完結社会〉の成立とも密接に関わる理由がある。それは、これまで戦後の人文科学を支えてきた人間理解、人間の理想こそが、ある面では〈自己完結社会〉を促進させるひとつの原動力となってきたと本書が考えているからである。
その代表格とも言うべきものを、本書では〈自立した個人〉の思想と呼んでいる。
その人間理解によれば、われわれはまず、伝統や権威、世間や権力といった外的なものに服従することなく、自ら思考し、自ら判断できる“強い個人”としての素養を身につけなければならない。そしてそうした個人が自発的に連帯することによって、強制や同調圧力とは異なる形の新たな共同がもたらされ、より良い社会が実現できるとされている。
注目したいのは、ここで人々がそうした理想状態に到達するためには、人間存在が自らの自立を阻むあらゆる抑圧から“解放”され、「存在論的な自由」を実現させなければならないと考えられてきたことである。
抑圧から解放されるという意味においては、この半世紀もの間、確かにわれわれはそれを着実に実現してきたと言える。貧困から解放され、伝統から解放され、地域社会から解放され、それによってわれわれは、それ以前の世代が経験したことのないほどの高水準の自由と平等を実際に獲得してきたはずである。
しかし同時にこうも言えないだろうか。その延長線上において、われわれはいまや、自らを抑圧する“他者そのもの”から、そして自らを縛る“身体そのもの”からも解放されつつある。そしてそれによって、実際われわれはいっそう「自由」で「平等」になるだろうと。
このことが示唆しているのは、〈自己完結社会〉が、単に科学技術が高度化した結果としてもたらされたのではないということである。むしろ〈自己完結社会〉は、われわれが人間の理想を実現しようとして、ある面では自ら望んで創りあげてきたものでもあるということである。
隣人たちとの濃密な人間関係から解放されるということは、そうした人間関係からの自由を意味するだけでなく、同時にそうした人間関係が必然性を持たなくなることを意味している。物事が生まれ持った身体によって左右されなくなることは、身体からの自由を意味するだけでなく、同時にそうした身体とともに生きる必然性が失われることをも意味しているのである。
ここで示唆されているのは、〈自立した個人〉の理想を追い求めることが、〈関係性の病理〉や〈生の混乱〉の克服につながるどころか、結果的に〈生の自己完結化〉と〈生の脱身体化〉を加速させ、われわれの「病理」をいっそう深刻なものにするおそれがあるという逆説である。
確かに〈自立した個人〉の思想が語る、自立や連帯といった言葉は、21世紀を生きるわれわれにとっては、やや古くさいもののように映るかもしれない。
実際ポストモダニズムやポスト構造主義、あるいは現代思想と呼ばれる一連の言説群――本書ではそれらを「ポストモダン論」と呼ぶ――は、まさにこうした自立や連帯の限界を指摘し、それに代わるアプローチとして登場した側面があっただろう。
しかし現実においては、〈自立した個人〉の思想に体現される人間理解は、いまでも根強く人文科学に根を下ろしている。このことは人文科学の現場において、いまでも“真の自由”、“真の平等”、“真の共生”なるものが漠然として想定され、目の前の不自由、不平等、非共生を批判し、その原因と見なされた抑圧や権力を告発することばかりに力が注がれていることからも分かるだろう。
ここで重要なことは、真の問題は〈自立した個人〉の思想が語る自立や連帯それ自体ではないということである。戦後の人文科学を支えてきたのは、一連の思想が体現してきたひとつの“人間観”であって、この人間観こそが真に問われるべきものだからである。
例えばそこでは、この世界の何処かに「本来の人間」(あるいは「完全な人間」)というものが存在することになっている。
「本来の人間」は、人間性が全面的に展開する人間存在の理想状態であるのだが、人間は生まれながらにしてさまざまな鎖に縛られているために、その至高の状態にはまだ一度も到達したことがない。それゆえわれわれは自らを鎖のもとから解放し、「本来の人間」へと向かって絶えず前進していかなければならないのである。
誰ひとりとして目撃したことがないはずのその姿が、なぜ人間本来の姿だと言えるのだろうか。そしてなぜ、その状態が人間にとって至高のものだと言い切ることができるのだろうか。そうしたことは不問のまま、ここでは「本来の人間」を想定するがゆえに、あらゆる不都合な人間的現実が否定される。
受け入れがたい生の現実、社会の現実は、本来のあるべき姿ではないからといって拒絶され、そこに想像された理想の人間、理想の社会が対置される。生身の現実から出発するのではなく、最初に理想の状態があって、それに合致するよう、あくまで現実の方をコントロールしようとする。
それは言ってみれば、「意のままにならない生」の現実を否定し、「意のままになる生」をどこまでも追い求めていく人間観なのである。
本書では、こうした人間観のことを指して〈無限の生〉の人間観と呼ぶ。そしてこの人間観こそが、〈自己完結社会〉における人間の“苦しみ”を理解する鍵になるものだと考えている。
例えばわれわれがどれほど「意のままになる生」を望んだとしても、人間には、人間である限り決して意のままにならないものがある。しかし〈生の自己完結化〉や〈生の脱身体化〉が進行することによって、本来意のままにならないものであったはずの対人関係や身体までもが、部分的にコントロールできるものとなった。
そのことがいわば、われわれに錯覚をもたらしているのである。いまやわれわれは、意のままになる他者、意のままになる関係性、そして意のままになる身体を無意識のうちに求めている。人間の生は、本来意のままになるべきものである。いや、もはやそこでは、意のままになる生こそが「正常」であって、意のままにならない生の現実は「非正常」であるとさえ言えるだろう。
そしてだからこそ、われわれは本当に意のままにならない生の現実に直面するとき、極度に乖離した理想と現実の間で引き裂かれてしまう。現実を受け入れることができずに立ち尽くしてしまう。そこに残されるのは他者や世間に対する、そして自己存在に対する絶望と憎しみ、あるいは虚無だけだろう。
おそらくわれわれが本当に必要としているのは、現実を否定する理想の微睡みなどではなく、「意のままにならない生」の現実に寄り添い、そのなかでより良き生とは何かを語ることのできる、新しい人間観を希求することである。
人間には、人間である限り逃れることのできない何かがある。そうした〈有限の生〉を正面から見据え、そこからわれわれの存在の歴史、人間存在の〈共同〉、〈役割〉、〈信頼〉、〈許し〉について再び語ること、そしてそうした〈有限の生〉を引き受けたうえで、人間存在がより良く生きるための方法とは何かを模索していくことなのである。
戦後の人文科学を支えてきたのは〈無限の生〉の人間観であった。そしてわれわれは、そうした人間観に共鳴し、それを信じ、過剰適応に陥った末、〈自己完結社会〉の成立へと至り、ついにはその人間観そのものに挫折したのである。
本書が独自のスタイルを採用するのは、このように本書が、それに代わるまったく新しい人間観の創出を企図しているからに他ならない。
本書は、筆者および筆者の共同研究者らによる10年にわたる研究成果である。筆者らは、こうして紡ぎだされた研究手法を「現代人間学」と呼び、その目指すところを「強度を備えた〈思想〉の創造」と呼んできた。
〈思想〉とは、「われわれがいかなる時代を生きているのか」、そして「この時代に人間をどのように理解すべきか」という根源的な問いに対して、ひとつの体系的な説明を試みた言説のことである。
そして「強度を備えた〈思想〉」とは、それ自体でひとつの世界観、人間観を体現できるだけの重厚さを備え、かつ移りゆく時代の不確実性や不透明性にも耐えうる思想、そして現実と肉薄する人々の内面にまで届きうる、言葉そのものの潜在力を備えた思想のことである。
われわれは〈自己完結社会〉の成立という未だかつてない事態を前に、人間を説明するための新たな概念、新たな言葉、そして新たな〈思想〉を必要としている。
何度でも言おう。われわれが必要としているのは、人間が生きることの悲哀や苦悩を無邪気な理想によって塗りつぶしていくことではない。かといって、人間が生きることの無力さと残酷さから、自己憐憫に沈んでいくことでもない。求められているのは、そうした哀苦や残酷さを一度は肯定し、なおわれわれが前を向いておのれの現実と対峙していくことができる人間の〈思想〉である。
そしてその要請は、“危機の時代”において、まさに哲学が、そして人文科学が、いかにその本分を全うすることができるのかという問題でもあるのである。