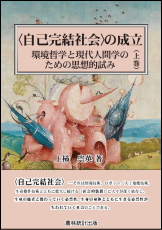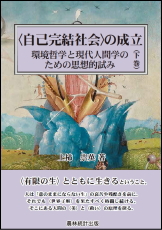用語解説
「赤子のロビンソン・クルーソーの比喩」 【あかごのろびんそんくるーそーのひゆ】
- 「問題は、このとき成人になった“彼”が、はたしてわれわれから見て“人間”と呼べるものになっているのかどうかということである。想定される解答は、それは「ヒト」ではあっても「人間」であるとは限らない、というものだろう。……この「赤子のロビンソン・クルーソー」の比喩は、〈人間〉というものにとって、〈社会〉の存在がいかに重要なものであるのか、そしてそれが身体能力や生活習慣だけでなく、言語、認識、思考に至るまで、いかに多岐に及ぶものであるのかを想起させるのに十分である。」 (上巻 108)
人間存在が、生物学的な「ヒト」を基体として、「社会的なもの」を媒介する(チューニングを受ける)ことによってはじめて人間存在として現前できることを、動物学者の小原秀雄による以下の一文を手がかりに、筆者が継承した比喩のこと。
- 「ロビンソン・クルーソーがもし本当に孤島に隔絶され、赤ん坊の時代からそこで育ったならば(育ったと仮定してであるが)、彼は人間であろうか。おそらくヒトではあるが人間ではないだろう。……[彼は]他の人間(社会)のなかで育てられなければならなかっただろう。少なくとも知能を働かすために、彼は人間と接触して人間的になっておく必要があった。……[もし彼に]その機会がなかったならば、形は人間でありヒトであっても、あるいは何一つできずに死ぬ可能性さえある」 (小原秀雄 「人間とは何か――人間学の建設のために」『人間の動物学』1974[1970]、季節社、p.263、[ ]内は筆者による)。